「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
旧車の売買と鑑定市場

ランクル200の最新リセールバリュー!旧車買取専門店が高く売るコツを解説
ランドクルーザー200系のリセールバリューが高ければ一度は乗ってみたいという人も多いでしょう。今回は、ランドクルーザー200系のリセールバリューの相場やリセールバリューが決まる要因、ランドクルーザー200系を高く売る方法などについて詳しく解説します。ランドクルーザー200系の購入や売却を検討中の人は参考にしてください。 ランドクルーザー200系のリセールバリューの相場 ランドクルーザー200系のリセールバリューの相場は、圧倒的な高値を維持しています。これは、高いオフロード性能や頑丈な車体は世界的にも認められており、経年や走行距離にそれほど左右されることなく国内外での需要が見込まれるためです。 ただし、昨今の中古車バブルによって高騰し続けていた相場は社会情勢の変化により収まりつつあるため、今後の推移については注視する必要があります。相場の高騰時に購入して数年後に売却すると、車両の残価率が大幅に下がる可能性があるため注意が必要です。 また、ランドクルーザー200系のリセールバリューの相場が高い一因として、パキスタンでの人気の高さが影響しています。ランドクルーザーが最も輸出されているパキスタンでは「製造年から5年以内」という中古車輸入規制があり、それが日本の中古車相場に大きく関係するためです。新車でランドクルーザーを購入するには関税の影響でかなりの高額となるため、船便で1ヶ月程度で輸入できる日本の中古ランドクルーザー200に人気が集中しています。 ランドクルーザー200系を手放すのならば、パキスタンの年式規制が終わる前に売却するのがよいでしょう。それ以前の年式の車両は、走行距離や車両の状態を問わず価値が急落することもあるため注意が必要です。 ランドクルーザー200系のリセールバリューが決まる要因 ランドクルーザー200系のリセールバリューが決まる要因について詳しく解説します。 製造年から5年以内の車両 ランドクルーザー200系は、製造年から5年以内までの車両のリセールバリューが特に高い車です。ランドクルーザー200系が最も輸出されているパキスタンでは中古車を輸入する際に年式規制があり、この規制の範囲内かどうかが日本の相場にも大きく影響を与えています。該当する車両かどうかで査定額が200万円ほど変わることもあるため注意が必要です。 エンジン変更後のモデル ランドクルーザー200系は、2009年のマイナーチェンジ後の新開発1UR-FE型エンジン搭載車が人気です。100系に搭載していた2UZ-FE型の改良版である従来のエンジンと比較すると、吸気側のみだったバルブタイミング制御を排気側にも追加したDUAL VVT-iへと進化させています。最高出力は30ps増加し、同時に燃費性能の向上と6速ATへの変更によりドライビングフィールもよりスムーズになりました。 2009年に追加された最上級グレードのZX系が人気 ランドクルーザー200系は最上級グレードのZX系が人気です。20インチのアルミホイールや電子制御式可変ダンパー、高耐久性のセミアニリン仕上げ本革シートなどを装備したハイエンドモデルといえるでしょう。悪路走破性の高いオフローダーであると同時に、最上級のサルーン仕様が幅広い層から求められています。 ランドクルーザー200系を高く売る方法 続いて、ランドクルーザー200系を高く売る方法について詳しく解説します。 ランドクルーザー200系の買取が得意な業者を選ぶ ランドクルーザー200系の買取が得意な業者を選ぶことで、より高く売れる可能性があります。ランドクルーザー200系は、日本国内だけでなく海外でも非常に人気の高い車です。国内にしか販売ルートを持っていない買取業者では、オークション相場に基づいた査定しかできません。 ランドクルーザーを専門に取り扱う業者であれば詳細査定の経験や売買実績が豊富であるため、高額査定が出やすいといえるでしょう。 足回りを中心としたメンテナンスをこまめに行う ランドクルーザー200系は、足回りを中心としたメンテナンスをこまめに行うことで高く売れる可能性があります。ランドクルーザー200系は、レジャーやオフロードで使用されることが多い車です。走行距離が長くなることによる足回りの劣化や、雪道・海岸沿いを走ることによる塩害への対策をしっかりと行いましょう。 リコール対策済みであること ランドクルーザー200系には、燃料ポンプやエアバッグの動作不良によるリコール対象車両があります。対象車両かどうかの検索はトヨタのホームページ上で車台番号を入力すれば検索できるため、未実施の場合はディーラーで無料の点検修理を受けましょう。不具合が万一発生すると、状態によっては車両の価値を大幅に下げてしまうため注意が必要です。 ランクル200の魅力と歴史 ランドクルーザー200系は、2007〜2021年に販売されたトヨタのSUVです。強靭なラダーフレームによる頑丈さと悪路走破性の高さへの信頼は絶大で、2019年には世界170ヶ国で販売され年間グローバル販売台数は約40万台にのぼります。また、豪華な内外装に加えて、ワイルドさと上品さを兼ね備えた外観デザインは新たなユーザー層も獲得しました。 ランドクルーザー200系は、歴代のランドクルーザーの中でも特に豪華装備といわれており、国内外の富裕層から絶大な支持を得ています。リセールバリューの高さや中古車価格高騰により、投資目的で購入するユーザーも少なくありません。 モータースポーツではダカールラリーでも活躍しています。過去13回に渡って出場し、市販車部門で11回の優勝(9連覇)に輝きました。この輝かしい実績や砂漠地帯でのタフな走りが、中東地域でのランドクルーザー200系の市場価値をさらに高めています。 基本スペック乗車定員........8名(官公庁向けのGXグレードのみ5名)駆動方式........フルタイム4WDエンジン........4.7ℓ V型8気筒DOHC 2UZ-FE型、4.7ℓ V型8気筒DOHC 1UR-FE型(2009年4月以降)

R32スカイラインのリセールバリューは高い?高く売るためのポイントを紹介
日産を代表する4ドアスポーツセダンおよび2ドアスポーツクーペとして人気が高いスカイライン。中でも、R32型はデビューから時間が経過しているものの、現在でも高い人気を誇ります。今回は、R32スカイラインのリセールバリューや高く売るポイントなどを解説します。 R32スカイラインのリセールバリューのポイント R32スカイラインのリセールバリューは、~200万円程度が相場です。実際のリセールバリューはグレードによって異なるため、査定してみなければわかりません。 買取相場の傾向を見てみると、4ドアセダンよりも2ドアクーペの方が高く買い取りされています。また、R32スカイラインの高性能スポーツグレードである「GT-R」は、プレミア価格として高額買取されるケースが多くみられます。 R32スカイラインを高く売る方法 ここからは、R32スカイラインを高く売る方法について紹介します。 基本的なメンテナンスをしておく 外装や内装、エンジンやトランスミッションなど、見える部分だけでなく、見えない内部の部分までしっかりとメンテナンスしておくと、高く買い取ってもらうことができます。 そのため、R32スカイラインを少しでも高く売りたいのであれば、定期的なメンテナンスを欠かさないようにしましょう。 ノーマルパーツに戻す R32スカイラインの中でも2ドアクーペは、スポーティな走行を楽しめるモデルとして高い人気を誇ります。 そのため、ホイールを交換したりエアロパーツを追加装着したりして、走行をより一層楽しめるようにカスタマイズしているケースも珍しくありません。このようなカスタマイズ車両は、そのままでも高く売れるケースがあります。しかし、カスタマイズのベース車両として売却した方が高く売れるケースの方が多いことから、ノーマル状態に戻した方がよいといえるでしょう。 まずは、売却するときはカスタマイズした状態で査定してもらい、ノーマルに戻した方が高く売れると判断された場合には、ノーマル状態にして売ることをおすすめします。 R32スカイラインの魅力と歴史 R32スカイラインは、1989年5月にデビューしたスポーティな走りを追求した4ドアセダンおよび2ドアクーペです。 シンプルな面で構成されたボディや絞り込まれたフロントノーズなどにより伸びやかなスタイリングが特徴となっています。用意されるボディタイプは、4ドアセダンと2ドアクーペの2タイプです。それぞれに2WDと4WDが設定されています。 また、オーバーフェンダーや専用フロントスポイラー&リアスポイラーなどを採用し、直列6気筒ツインターボエンジン(RB26DETT)を搭載した「GT-R」も用意されています。 さらに、NISMO、オーテックバージョン、N1など、さまざまなバリエーションを展開していたこともR32スカイラインの特徴です。 【R32スカイラインの主なスペック】 ボディサイズ 4ドアセダン:全長4,580mm×全幅1,695×全高1,340mm2ドアクーペ:全長4,530mm×全幅1,695mm×全高1,325mmGT-R:全長4,545×全幅1,755mm×全高1,340mm エンジン 直列4気筒1.8L直列6気筒2.0L直列6気筒2.5L(1991年8月以降)直列6気筒2.6Lツインターボ(GT-R)
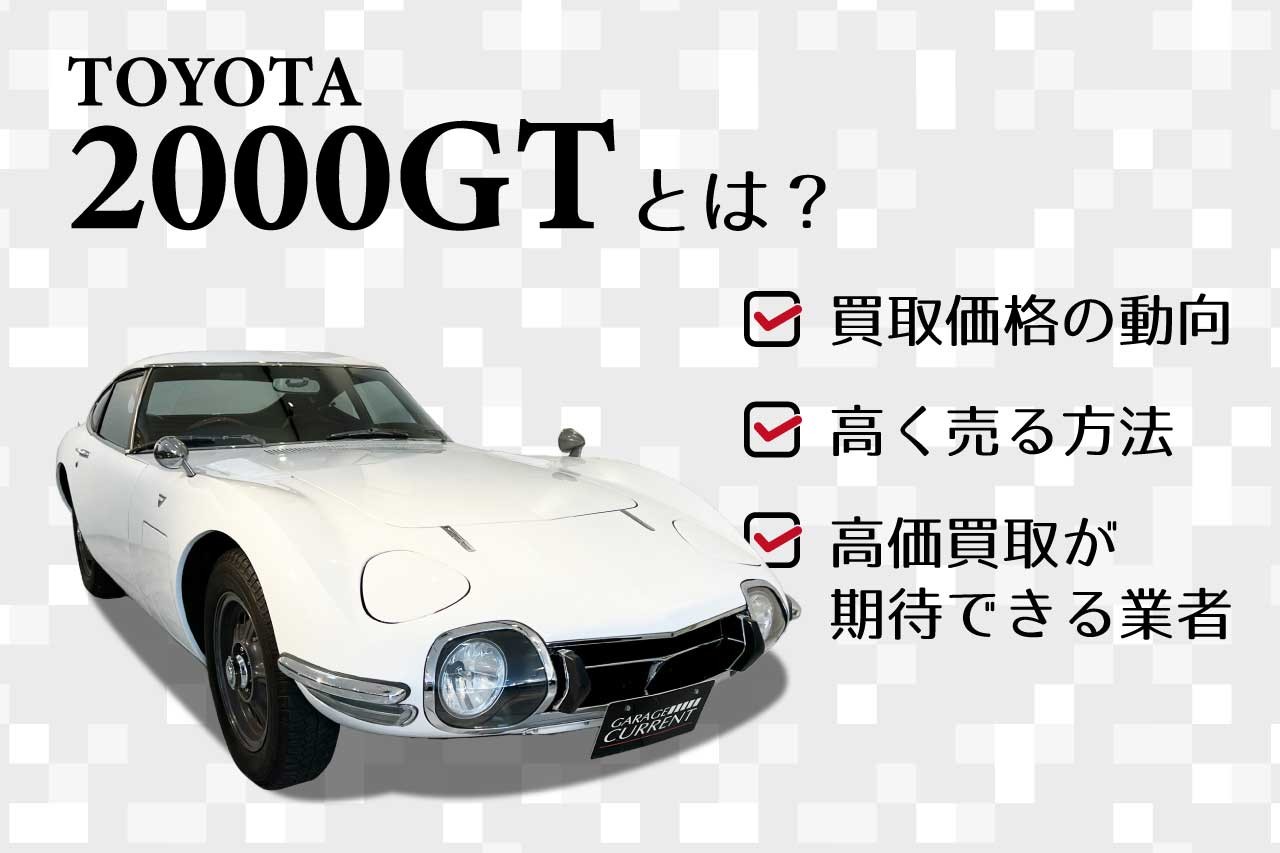
トヨタ 2000GTとは?値段・価格動向や歴史について解説
現在も世界のスーパーカーファンを魅了するトヨタ 2000GTを詳しく知りたい人も多いでしょう。今回は、トヨタ 2000GTの概要、買取価格の動向、トヨタ 2000GTを高く売る方法や高価買取が期待できる業者の特徴について解説します。トヨタ 2000GTの売却を検討中の人は参考にしてください。 トヨタ 2000GTとは? まずは、トヨタ 2000GTについて詳しく解説します。 エクステリアの特徴 トヨタ 2000GTのエクステリアの特徴は、リトラクタブルヘッドライトのファストバッククーペであることや、現在でも異例といえる専用デザインのマグネシウムホイールが採用されている点です。当時のスポーツカーの定番デザインともいえるロングノーズ&ショートデッキスタイルは、5ナンバーのコンパクトボディ(ボディサイズは全長4,175mm、全幅1,600mm、全高1,170mm)ながら流麗なデザインとして世界中から高い評価を得ています。 ボディカラーはペガサスホワイト、ソーラーレッド、サンダーシルバーメタリックの基本3色で、特注色(後期型で正式採用)のベラトリックスイエロー、アトランティスグリーン、トワイライトターコイズメタリックを合わせた計6色が販売されました。また、ゴールド塗装の特別車両も3台(前期型の2台はそれぞれToyota USA Automobile Museum、ヤマハ発動機コミュニケーションプラザに展示。後期型の1台は所在不明)のみ存在します。 インテリアの特徴 ウッドのステアリングとインパネ、シフトレバーに多眼メーターの組み合わせにより現在の車にはない重厚感があることが、トヨタ 2000GTのインテリアの大きな特徴です。ウィンカーやライトの操作系はメーター周りに配置されたトグルスイッチで、ノスタルジーを感じる人も多いでしょう。また、サイドブレーキがトラックなどで採用されているステッキ型となっており、スポーツカーとしては特異な点です。 エンジンの特徴 トヨタ 2000GTのエンジンは直列6気筒DOHCで、クラウン用に開発されたM型(直列6気筒SOHC)をヤマハ製のDOHCヘッドに換装した3M型です。0-400m15.9秒、最高速度220km/hは当時の世界トップレベルをマークしています。 さまざまなシーンで活躍した功績 トヨタ 2000GTはさまざまなシーンで活躍した功績があります。モータースポーツでは鈴鹿500km・1,000kmレースや富士24時間レースといった耐久レースで優勝し、発表当時のスピードトライアルで3つの世界記録と13におよぶ国際記録を樹立しました。また、日本車として唯一映画「007シリーズ」のボンドカーとして劇中に登場しており、トヨタ 2000GTとトヨタの名前を世界中に広げています。 トヨタ 2000GTの価格動向 トヨタ 2000GTは新車販売価格は238万円で現在に換算すると2,000万円級の高級スポーツカーであり、1967〜1970年の3年間でわずか337台の生産台数でした。このためトヨタ 2000GTは「幻の名車」と呼ばれるほどにその希少価値が評価されています。 海外オークションでは驚くべき価格で取引されています。2020年10月にはアメリカで開催された「RMサザビーズ」にて約9,560万円(91万2,500ドル)で、2022年3月には同じくアメリカで開催された「アメリア・アイランド・オークション」にてなんと約2億9,300万円(253万5,000ドル)で落札されました。この個体は、シャシーナンバー「MF10-10001」のトヨタ2000GTの第1号車であるがゆえに超高価格がつけられました。 2023年3月には、フランスで開催された「RMサザビーズ」で約8,830万円(62万3,750ユーロ)にて落札。条件や状態によって価格差はあるものの、やはり「トヨタ 2000GT」のブランドには数千万円級の価値があるといえます。 トヨタ 2000GTを高く売るためには? トヨタ 2000GTを高く売るためには、日頃からしっかりとしたメンテナンスを行うことが重要です。新車登録から50年以上が経過した車のため、レストアを行っていることも多いでしょう。しかし、レストアはあくまで研磨や洗浄分解、バランス取りにより新車に近い状態に戻す作業です。新品の純正部品が入手できるのであれば、可能な範囲で部品交換をしておくことでさらに高額査定となる可能性が高いでしょう。 トヨタのGRヘリテージパーツプロジェクトでは、既に廃番となっていたトヨタ 2000GTのトランスミッションやデファレンシャル関連部品及び消耗品類が純正部品として復刻されています。Toyota Gazoo Racingサイトで販売されているため、レストアやメンテナンスに活用するとよいでしょう。 トヨタ 2000GTの高価買取が期待できる業者の特徴 続いて、トヨタ 2000GTの高価買取が期待できる業者の特徴について詳しく解説します。 買取実績がある トヨタ 2000GTの買取実績がある業者であれば、高価買取に期待できます。トヨタ 2000GTは、発売から50年以上が経過した、世界中のスーパーカーファンの垂涎の的です。実績もない一般的な買取業者ではとても取り扱いできません。 売却する際には、過去にトヨタ 2000GTの買い取った実績があるかどうかを確認しましょう。加えて、他の名車や希少車を数多く取り扱っている業者であればより安心して任せられます。 ちなみに、旧車王では過去に二度トヨタ 2000GTを買い取りました。1967年式と1968年式、いずれも前期型です。実績をもとにした高価買取が可能であるため、私たち旧車王にぜひ査定をお任せください。 二重査定をしない 二重査定とは、買取契約後に引き取った車両の再査定を行い、不具合があった場合に査定額の減額請求やキャンセルを行う行為です。お客様にとって不誠実な対応でありながらも、中古車買取業者の間で横行しています。なぜ二重査定する事態が起こるのかというと、車に対する知識もノウハウも未熟なままに査定するため、一度で車両の細かな状態までチェックできないからです。逆に考えると、二重査定を一切しない業者は、一度の査定でしっかりと車両のコンディションを見抜ける実力をもっているといえます。大事なトヨタ 2000GTを売却するなら、確かな知識とノウハウをもち、誠実に査定してくれる業者を選びましょう。 希少な車の買取を得意としている トヨタ 2000GTの買取は、希少車を数多く取り扱っている業者に依頼すると安心です。希少車の査定は知識と経験がなければ非常に難しく、販売面でも個人顧客や販売ルートなどを確立していなければ信頼や実績を得られません。 トヨタ 2000GTはあまりにも珍しい車のため専門店はほとんど存在せず、投資家やブローカーが取引に関与する場合が多い傾向にあります。しかし、オーナーが納得できる適正な査定を考えると、希少な車の買取を得意としている専門業者への依頼がおすすめです。

持ち家を検討している場合、先にクルマを買うのはアリorナシ?
筆者の友人・知人の何人かが自動車関連業や不動産業に従事している。 そこで話題になるのが「ローンに関すること」だ。 個人情報があるので親しい間柄であっても詳しくは教えてくれないが、最近多いのが「クルマのローンを先に組んでいて、そのあとに家を買おうとして住宅ローンの審査で引っかかるケース」だという。 クルマのセールスの友人曰く、旦那さんの方が独身時代に「今のうちに買っておかないと後で買えなくなる」と、勢いで趣味車や自分好みのクルマをローンを組んで契約、その残債がネックとなってすんなり住宅ローンの審査が通らなかった……というケースがしばしばあるとか。 家を買うとなると、結婚して子どもが産まれて・・・といった具合に、比較的若い、いわゆる「子育て世代」が多い。 友人であるクルマのセールスも、「正直1台でも多く売りたいのはヤマヤマだが、子育て家族と商談する場合『すでに持ち家か、あるいは近々購入予定があるか』を聞くようにしている」という。 理由は前述のとおりだ。 筆者自身も、取材を通じ、結婚して子どもが産まれて、せっかく家を建てるならいっそビルトインガレージ付き…といった未来予想図を描いている20代〜30代のクルマ好きの方と知り合う機会が多い。 たしかに、結婚して子どもが産まれたら、家のクルマはミニバンかSUVなど、実用的な選択肢のなかで選ばざるを得ない。 ましてや趣味車を増車するなど論外だ(よほど稼いでいれば別だが)。 筆者はファイナルプランナーのような専門知識を有する立場ではないが、自身の体験と、現場からの声を備忘録的にまとめておこうと思う。 今回は特にそんな方たちに向けた予備知識として、記憶の片隅に留めてもらえたら幸いだ。 ■かつて「月賦払い」なんていわれていた時代もあった 会話のなかで「月賦(げっぷ)」というキーワードが出てきてといってピンとくるのは昭和世代だろうか……。 現代ではローンという言葉の方が一般的だと思う。 職業や年収、クレヒス(クレジットヒストリー)に代表される信用情報……などなど。 ありとあらゆる要素が加味されたうえでの「最大公約数=審査結果または融資額」ということを意味する。 つまり、ローンが組めたということは「一定の社会的な信用があると認められた」わけだ。 いっぱしとして認められた、ということかもしれない。 ■ローンの審査基準は謎。そして一律ではない ローンの審査基準は会社によってまちまちで、A社では断られたけれど、B社ではクリアできたというケースも少なからずあるようだ。 これはクルマおよび住宅ローンいずれも共通していて、いろいろな攻め方があるように思う。 ただ、最初にNGが出たあとすぐに別のローン会社に審査を依頼すると不利という話も耳にした。 イチかバチか的なローン申請をできるだけ避けることはもちろん、普段から支払い関係をクリーンにしておくのが懸命だろう。 また、すでに住宅ローンを組んでいて、ローンや残価設定ローンなどでクルマを購入する場合「高額な住宅ローンを組めるほど支払い能力がある」と評価するか「すでに高額なローンを組んでいる」と判断するケースもあるという。 ■クルマを買う前に押さえておきたい、住宅ローンを組む際にチェックすべきポイント 筆者は、フリーランス時代に2度住宅ローンを組んだことがあるが、その際、別々のメガバンクを利用した。 面談の際に、ここぞとばかりに担当者さんを質問攻めにして教えてもらったことをまとめておきたい。 家を建てる前にクルマが欲しいといって譲らない旦那に頭を抱えているそこの奧さん、これを見せてあげてください。良識ある旦那さんなら、ヘタに統計論とか理詰めで攻めるよりも冷静に現実を受け止めてくれるはずなので。 ●どれくらい頭金を用意できるか 住宅ローンであれば購入金額の20%までが目安とされる。これはクルマも同様だが、決して安くはない金額といえる ●他のローンの残債 特に響いてくるのがクルマのローン。まずこれを完済しないと住宅ローンを組ませてもらえないケースもあるので要注意 ●過去のローン実績(組んだ回数) いわゆる現金派の人がいるが、たとえ高収入であってもローンを組んだ実績がないと未知数と見なされる可能性大 ●過去のローンの完済実績(繰り上げ返済を含む) ここはかなり重視されるようだ。繰り上げ返済も加点ポイントとなる ●職業(正規/非正規/自営業を含む) 会社員だけでなく、公務員や士業、看護師など、安定性や誰もが知るまたは資格を活かして生計が立てられると見なされるようだ。その点、非正規およびフリーランスは不利(過去3期分が判断基準) ●勤続年数 勤続3年以上が望ましいが、最低1年以上であれば可能性はゼロではなさそう。転職直後であっても前職の勤続年数が長いと加点となるようだ ●年収 当然ながら多ければ多いほど有利。年齢が低ければ、年収が低くても将来性(若い)ということで加点となるケースも ●過去のローンのお手つき(滞納)の有無 1ヶ月以上の滞納、3ヶ月以上、複数の滞納でそれぞれ減点(あるいはローン不可)と見なされるようだ 心配であれば、CICに問い合わせて自身の信用情報をチェックしてみるといいかもしれない。 CIChttps://www.cic.co.jp/ CICについて(YouTube動画)https://www.youtube.com/watch?v=wuFubU09uJg ●保証人のおてつきの有無 これ、意外と盲点だという。本人はまっさらでも、保証人になった当人がブラックだったりするとアウト。ローン審査時に初めて知ったというケースもあるので事前に要確認 ●各種税金や保険料の納付状況 会社員であれば強制的なので問題なさそうだが、フリーランスだと忙しさにかまけてつい滞納していた…となりがち。要注意ポイント ■【超重要】携帯電話やスマートフォンの料金滞納は絶対にNG いっぱしの社会人であれば「言わずもがな」かもしれないが、この記事を未成年の方が読んでくれている可能性もある。 これは他のメディアに寄稿している記事で何度も記しているが、携帯電話(現在はスマホだろうか)の料金滞納はぜったいにNGということだ。 「1度くらい滞納しても問題ないでしょ」と思うなかれ。 こういってはナンだが「日常的に使うモノの支払いが滞るようなら、はるかに高額なクルマや住宅のローンの毎月の支払いもきちんとできるか怪しい」と判断されてしまうわけだ。 これは故意に支払いを忘れたケースはいうに及ばず、当然ながら「うっかり忘れていた」も含まれる。 故意だろうがうっかりだろうが、自宅に督促状が届いたら即対応。 もし、手元に現金がなければ、すぐに親族や友人知人に借りてでも(ここでノンバンクに手を出すのは本末転倒だが)対応すべき最優先事項だと断言しておきたい。 ■結論:近々持ち家を検討している人が先にクルマを買うのはアリorナシ? 筆者なりの経験ならびに、セールスの友人・知人たちの見解は「ナシ」だ。 ローンはもちろんのこと、現金一括であったとしても、持ち家を購入するための頭金を削っていることは事実だからだ。 FIREできるほどの資産があったり、年収が何千万もあって、大して気にしなくていいというのであれば話は別だが、少数派だろう。 将来、結婚を約束している相手がいない場合はやむを得ないとしても、数年以内に結婚して持ち家の購入を考えているとしたら……。 ローン(サブスクや残価設定も含む)を組んでクルマを買うのは待った方がいい。 頭金ゼロ、60回払いでミニバンを買ったとして、その残債が住宅ローンの審査のときに引っかかってくる。 かなりの確率で住宅ローンの融資額が減るだけでなく、融資そのものが通らない可能性もある。 または「クルマのローンを完済すれば住宅ローンの審査を通すか、●●●万円まで増やせる」といった条件が課せられたりする。 どうしても欲しいクルマがある、必要に迫られているとしたら、クルマは現金や親ローン(オススメしていいものか………)で対応し、少しでも住宅ローンの融資が通りやすいまたは融資額が増えるようにしたい。 最近はクルマのサブスクも一般化しつつあるとはいえ、借金であることに変わりはない。 解決策として「おまとめローン」のように、家とクルマ、同じタイミングでローンを組んでしまうという手もある。 実際問題、毎月の返済額に驚いて、クルマどころではなくなってしまう可能性大だが……。 ■余談:フリーランスは不利? それほど高額なクルマを購入したことがなかったかもしれないが、筆者がフリーランス時代にもローンは組めた。 しかし、住宅ローンとなるとかなり苦労したことも事実だ。 情けない話ではあるが、何しろ融資額が低すぎた。 審査のとき、売上の金額には目もくれず、年収の数字しか見てくれない。 仮に年間の売上が1000万円だとして、年収を250万円で申告していたら、後者の基準で判定される。 銀行の方に聞いたところだと、3期連続で300万円くらいの年収がないと話にならないらしい。 とにかくフリーランスは社会的な信用が低いということを身に染みて味わった。 テレビで「芸人、家を買う」という企画を観たことがあったが、まさにあれだ。 いまは売れっ子芸人でも、来年、5年後、10年後はどうなっているか未知数だ。 いま以上に売れっ子になって世田谷に豪邸が建てられるレベルに到達しているかもしれないし、「あの芸人はいま?」の特集で紹介されるほど過去の存在になっているかもしれない。 はたまた、体調を崩して療養しているかもしれない。 不確定要素が多く、長期に渡って支払い能力があるかどうかは分からないと判定するようだ。 将来、独立を考えているとしたら、クルマはともかく家は先に手に入れておいた方がいいかもしれない。 はたまた、キャッシュで買えるくらいゴリゴリに稼いでしまえば何の問題もないのだか……健闘を祈る! [画像/Adobe Stock ライター/松村透]

レガシィツーリングワゴンのリセールバリューのポイントは?高く売る方法や魅力と歴史についても解説
レガシィツーリングワゴンのリセールバリューが高ければ、一度は乗ってみたいと思う人も多いでしょう。今回は、レガシィツーリングワゴンのリセールバリューのポイントや高く売る方法、レガシィツーリングワゴンの魅力と歴史について解説します。レガシィツーリングワゴンの購入や売却を検討中の人は参考にしてください。 レガシィツーリングワゴンのリセールバリューのポイント レガシィツーリングワゴンのリセールバリューには、特別仕様車や数量限定車、スポーツモデルであるかどうかなどが大きく影響します。また、一般的なモデルでも状態によっては高値になることもあるため、レガシィツーリングワゴンの価値を理解している買取業者に相談するとよいでしょう。 レガシィツーリングワゴンを高く売る方法 続いて、レガシィツーリングワゴンを高く売る方法について詳しく解説します。 走行性能に関わる部分を重点的にメンテナンスしておく レガシィツーリングワゴンは、走行性能に関わる部分を重点的にメンテナンスしておくことで高く売れる可能性が高まります。スポーティーな性能に注目されているため、エンジンオイルや消耗品などの交換は必須といえるでしょう。また、点検整備記録簿に法定点検などの整備記録があると好印象を与えられるため、メンテナンスの一環として行うことをおすすめします。 高年式・低走行 レガシィツーリングワゴンは高年式・低走行な車両が人気です。スポーティーな性能が注目される車とはいえ、ファミリーユースやレジャー目的で購入されることも多く新車登録から10年以内、走行距離5万km以下の車両は高額査定となる可能性が高いでしょう。 DIT直噴ターボ搭載エンジンは対策が必要 5代目レガシィツーリングワゴンは、2.0ℓ DIT直噴ターボモデルが人気です。トヨタ86の兄弟車BRZに搭載されているFA20型エンジンを直噴ターボ化したハイパフォーマンスモデルで、300psを発生させます。レガシィツーリングワゴンの最終型ハイパワーモデルとして、リセールバリューが非常に高いといえるでしょう。 ただし、DIT直噴ターボモデルは異常燃焼によるエンジン故障でリコールが出ています。これはエンジンコンピューターの不適切なプログラムが原因です。ECU(電子制御ユニット)を対策プログラムに書き換えることで改善するため、未対策の対象車両(2012年4月19日〜2014年6月17日製造分の10,143台)はすぐにディーラーで点検を受けましょう。 エアロパーツ&サンルーフ装着車 レガシィツーリングワゴンは、スポーツワゴンらしくエアロパーツ&サンルーフ装着車が人気です。それぞれ単体で査定額が10〜20万円ほどアップすることが多いため、リセールバリューの高さを狙うなら購入時にチェックしておくとよいでしょう。 ボディカラーは白か黒が人気 レガシィツーリングワゴンのボディカラーは白か黒が圧倒的に人気です。特に白や黒で純正もしくはSTiのエアロパーツ付きであると、リセールバリューがアップしやすい傾向にあります。 レガシィツーリングワゴンの魅力と歴史 レガシィツーリングワゴンは、1989〜2014年にスバルが販売したステーションワゴンです。スバルの特色であるボクサーエンジンを搭載し、優れたワゴンユーティリティや走行安定性の高さ、モータースポーツ向けに開発されたWRX STiなどのイメージでスポーツワゴンの代名詞となりました。 1990〜1993年に参戦したWRCではわずか1勝という結果に終わるも、その後の15年に渡るスバルのWRCでの栄光の礎を築いたのがレガシィだったと評価されています。この活躍がスバルとボクサーエンジン&AWDというブランドを作り上げたといえるでしょう。 初代が発売された1980年代はスバルが倒産の危機に陥っており、レガシィツーリングワゴンが起死回生の大ヒットとなったのは有名な話です。なお、レガシィツーリングワゴンは5代目を最後に廃止されて、後継車種であるレヴォーグにその特徴が受け継がれました。レガシィは2019年以降は北米のみで販売され、日本国内では派生モデルのレガシィ アウトバックの販売が継続されています。 【5代目(最終型)モデル 基本スペック】 販売期間 2009~2014年 乗車定員 5名 駆動方式 4WD エンジン ・2.5L 水平対向4気筒DOHC EJ25型・2.5L 水平対向4気筒DOHCターボ FB25型・2.0L 水平対向4気筒DOHC直噴ターボ FA20型

日産 フェアレディZ(Z34)のリセールバリューは高い?相場や高く売るコツを紹介
2ドア2シータークーペ/オープンスポーツカー「フェアレディZ(Z34型)」は、日産の代表的なスポーツカーの1つです。フェアレディZののリセールバリューは高いのでしょうか。今回は、フェアレディZの中のZ34型フェアレディZのリセールバリューについて紹介します。Z34のリセールバリューについて気になっている方は参考にしてみてください。 フェアレディZ Z34のリセールバリューの相場 Z34型フェアレディZのリセールバリューの相場は、平均で250万円程度です。グレードや年式などによっては350万円程度になるケースもあるものの、全体の相場は200万円前後で推移しています。。 Z34型フェアレディZは2008年12月にデビュー。販売開始当時のグレードはベースグレード/Version T/Version S/Version STの4グレードで、価格は362万2,500円〜446万2,500円でした。 2023年時点でZ34のデビューから15年が経過しているものの、販売開始時の50%以上の価格を維持していることから、リセールバリューは良いと言えるでしょう。 フェアレディZ Z34のリセールバリューのポイント ここからは、Z34型フェアレディZのリセールバリューの傾向を解説します。売却するときや今後Z34を中古で購入するときの参考にしてみてください。 買取価格相場は高め Z34型フェアレディZの買取相場は、高めで推移しています。そのため、どのグレードであっても高価買取される可能性が高いでしょう。 このような高い買取相場となっている理由は、歴史ある希少な国産スポーツカーであるためだと考えられます。また、海外では「Nissan Z」として販売され、国内外問わず高い人気を維持していることも買取相場が高くなっている理由と言えるでしょう。 また、Z34にはMTとATが用意されています。どちらのトランスミッションでも高価買取されますが、買取価格を比較をするとATよりMTの方が高い買取額になるケースが多いようです。 NISMOや台数限定モデルは高額買取される傾向がある Z34型フェアレディZには、台数限定モデルやスポーツグレードの「NISMO」も用意されています。 これらの限定モデルやスポーツグレードは、ベーシックなモデル(ベースグレード/Version T/Version S/Version ST)よりも高額査定が期待できます。 リセールバリューが高いZ34を求めるのであれば、NISMOや限定モデルなどを選ぶとよいでしょう。 フェアレディZ Z34を高く売る方法 Z34型フェアレディZを高く売るためには、どのような方法があるのでしょうか。ここからは、Z34を高く売るコツについて紹介します。 NISMO仕様の場合はカスタムパーツを取り外さない メーカーカスタマイズのNISMOは、パーツを取り外さないようにしましょう。 NISMO純正パーツが取り外されていると本来の性能を発揮できず、売却時にマイナス評価となってしまいます。NISMOとは呼べなくなってしまうため、パーツは装着したまま売却しましょう。 足まわりやエンジンを入念にメンテナンスしておく フェアレディZは日産を代表するスポーツカーであるため、走行性能もセールスポイントのひとつです。そのため、足まわりやエンジンなど、駆動系のメンテナンスは欠かさずに行っておきましょう。しっかりと手入れがされていれば、売却時の評価も高くなります。 フェアレディZ Z34の魅力と歴史 フェアレディZは、1969年の初代(S30型)発売以降、世界中のユーザーから支持されてきたスポーツカーです。 2008年12月にデビューしたZ34型は、Zらしさであるハイパフォーマンス・デザイン・ハイバリューを盛り込みながら、パフォーマンスや質感をより進化させていることが特徴となっています。 走行性能の面では、ショートホイールベース化、軽量化、VQ37VHRエンジン(3.7L V6エンジン)、シンクロレブコントロール付6速マニュアルトランスミッション/マニュアルモード付7速オートマチックトランスミッションの搭載などにより「走る、曲がる、止まる」を進化させました。 質感の面では、スポーツカーとしての機能性と質感の高いインテリアを両立し、ドライバーとコックピットの一体化を目指しています。 【Z34型フェアレディZの主なスペック】 サイズ 全長4,250mm×全幅1,845mm×全高1,315mm エンジン 3.7L V型6気筒 トランスミッション 6速MT/7速AT(マニュアルモード付き) 駆動方式 FR(後輪駆動) 発売開始時期 2008年12月 価格(デビュー当時) 362万2,500円〜446万2,500円

レジアスエースバンのリセールバリューのポイントは?高く売る方法や魅力と歴史についても解説
レジアスエースバンがハイエースバンの姉妹車であることを知らない人も多いでしょう。本家ハイエースと同じリセールバリューであれば、購入してみたいと考える人も多いはずです。今回は、レジアスエースバンのリセールバリューのポイントやレジアスエースバンを高く売る方法、レジアスエースバンの魅力と歴史について解説します。レジアスエースバンの購入や売却を検討中の人は参考にしてください。 レジアスエースバンのリセールバリューのポイント レジアスエースバンのリセールバリューのポイントは、姉妹車であるハイエースと同じです。広いユーティリティに運転のしやすいボディサイズ、外観デザインやスペックなどに違いはありません。トヨタの販売チャンネルの違いによって名称が異なるだけのため、リアハッチのエンブレムと説明書以外はハイエースとまったく同じです。 レジアスエースバンはバンと福祉車両のみのグレード設定のため、ハイエースのようにワゴンやコミューターは選択できません。しかし、バン仕様でもワゴンに劣らない豪華仕様のスーパーGLが存在し、カスタム車やキャンピングカーのベース車両としてリセールバリューは高値で安定しています。名前が違ってもハイエースと同等のリセールバリューがあるといってよいでしょう。 レジアスエースバンは国産のバンとして屈指のリセールバリューの高さを誇るハイエースに劣らない人気があり、名称の違いではその価値は左右されません。キャンピングカーブームに影響されることなく、今後も高いリセールバリューは続くでしょう。 レジアスエースバンを高く売る方法 続いて、レジアスエースバンを高く売る方法について解説します。 内装はきれいにしておく レジアスエースバンは、内装をきれいにしておくことで高額査定となる可能性が高い車です。商用車として使用されることも多いため、積み荷で内装がぼろぼろになっていると査定で減額されてしまうこともあるでしょう。荷室のキズ防止用トリムカバーやラゲッジ用マットを使用し、新車購入時から傷や汚れを対策しておくことで高額査定が期待できます。 高年式・低走行 レジアスエースバンは、高年式・低走行の車両が高く売れます。新車の納車が長期化している状況では、状態のよい車両が新車の車両本体価格並みで中古車販売された事例もあるほどです。特に、新車保証が継承できる最終モデルは高額査定が見込めるでしょう。 圧倒的人気のスーパーGL レジアスエースバンは、上級グレードのスーパーGLが圧倒的な人気を誇ります。廉価グレードのDXも人気で、高いリセールバリューを維持しています。しかし、スーパーGLは「グランドラグジュアリー」の名を冠することからもわかるように、大人5人がゆっくりとくつろげるリアシートや、ワゴンやミニバンにも劣らない豪華仕様が特徴です。 ビジネスだけでなくファミリーユースにも絶大な人気のグレードで、リセールバリューを意識して購入するのであればスーパーGL一択といえるでしょう。また、特別仕様車 スーパーGL DARK PRIME(1〜2)などは、ダークメッキやスパークリングブラックパールクリスタルシャインといったダーク系色で彩られ非常に高い人気を博しています。 レジアスエースバンの魅力と歴史 レジアスエースバンは、1999〜2020年に販売されたトヨタのキャブオーバー型バンです。販売チャンネルの違いによってハイエースとは異なる名称で、バンのみ取扱いが開始されました。そのため、2020年にトヨタが全車種の全店舗取扱いを開始したのを契機に販売が終了しています。 レジアスエースバンは初代 H100系、二代目 H200系ともにハイエースと共通の構成で生産されており、広大な室内空間やカスタムパーツの豊富さなどその魅力はハイエースとまったく同じです。4ナンバーサイズの取り回しのしやすさや、頑丈で壊れにくい点も多くの人に支持される理由といえるでしょう。 【基本スペック】 初代 H100系 販売期間 1999~2004年 乗車定員 2~10名 駆動方式 FR/4WD エンジン ・2.0L 1RZ-E(ガソリン仕様)・2.4L 2RZ-E(ガソリン仕様)・2.0L 1TR-FE(ガソリン仕様)・3.0L 5L(ディーゼル仕様) 二代目 H200系 販売期間 2004~2020年 乗車定員 2~10名 駆動方式 FR/4WD エンジン ・2.0L 1TR-FE(ガソリン仕様)・2.0L 2TR-FE(ガソリン仕様)・2.5L 2KD-FTV(ディーゼル仕様)・3.0L 1KD-FTV(ディーゼル仕様)・2.8L 1GD-FTV(ディーゼル仕様)

日産マーチが生産終了?マーチとはどんな車なのかについても解説
日産マーチは、街中を歩くと毎日のように見かけるほど多くのユーザーに愛された車です。そのマーチが生産終了するのをご存知の方も多いことでしょう。今回は日産マーチの生産終了と海外での動きやマーチという車について解説します。マーチの購入を検討中の方は参考にしてください。 マーチが生産終了 マーチの国内販売向け生産が終了となりました。今後は在庫限りの販売となり、4代目の現行型で40年の歴史に幕を閉じます。国内での販売が終了する背景には日産の電気自動車やハイブリッド車の開発への経営資源振替えがあるとされており、世界的なEVシフトに向けた新ジャンルへの移行のための動きといえるでしょう。 海外ではマーチの販売が継続 海外に目を向けると、車名を「マイクラ」に変更して販売されている欧州では2017年に5代目が登場しており欧州と南アフリカ共和国で販売を継続、メキシコなどでもマーチの名前で生産及び販売が継続されます。日本とは異なり販売が継続される地域には現地工場があることも多く、輸送コストやニーズの面で事情が異なるのが理由です。 そもそもマーチとは マーチは、1982年から40年間に渡り日産が販売しているコンパクトカーです。初代マーチの発売当時は1ℓエンジンを搭載する車が各メーカーからラインナップされており、リッターカーの名称で大きな市場を築いていました。その中でもマーチはモデルチェンジサイクルが長く、モータースポーツ向けのモデルが販売されるなど多くのユーザーを魅了した車です。 初代マーチは、世界的に有名なイタリアのカーデザイナーであるジョルジェット・ジウジアーロ氏が企画を持ち込んで開発がスタートしました。車名であるマーチも公募により選出され、大きな話題と人気を得た世界戦略車でもあります。デザインのシャープさと運転のしやすいコンパクトさもあり国内では63万台超、欧州やカナダなども含めると100万台超が販売されました。 1992年に登場した2代目マーチは、国内外ともに高い評価を得て欧州カー・オブ・ザ・イヤーを日本車として初めて受賞しています。国内での日本カー・オブ・ザ・イヤー、RJCカー・オブ・ザ・イヤーとのトリプル受賞を果たした日本車は、1999年に販売開始されたヴィッツまで登場していないほどの快挙といえます。 その後は欧州車のイメージが強い3代目、4代目へとモデルチェンジしていき、いずれも堅調な販売台数をあげています。 また、コンパクトな街乗り車というイメージが強いマーチは、モータースポーツでも活躍しています。JAF公認のワンメイクレース「マーチカップ」が1984年から開催されており、特に初代は全日本ラリー選手権AクラスやWRCでの入賞により現在でも旧車として高い人気を誇っています。

10年以上のクルマを手放すなら「旧車王」!50代以上の方々に人気の理由とは?
旧車王とは? 10年以上経過したクルマの買取に特化して20年以上の買取専門店です。クルマを熟知したプロが価値を見極めて鑑定するため、二重査定は絶対になく、納得の適正買取価格で安心して売却をすることが可能です。 利用者の半数以上が50代の方々であることから、長くクルマに乗られてきたクルマ好きの方からご好評いただいています。 お客様の声の一部を紹介します。 ■Oさん(80代・男性)旧車王に連絡後すぐにI氏が来宅してくれたのは良かったと思う。又、処理も早く満足している。クルマに対するエピソードは多くあるが、44年間も役立ってくれて感謝している。次のユーザーとなられる方に大切に使ってもらえることを心から願っている。 ■Fさん(60代・男性)とても大切に乗ってきたクルマなので、自分以上に大切にしてもらいたいと思います。担当の方はとても信用出来る方とお見受けしましたが、その通りでした。ありがとうございます。 ■Nさん(60代・男性)若い社員の方でしたが、知識も豊富で誠実な方でした。とても気持ちよく対応いただきました。 神奈川県横浜市を拠点とし、全国47都道府県どこへでも査定にいきます。社内基準をクリアした経験豊富な鑑定士が最短当日で査定にいくため、日程調整もカンタンにできます! 条件に当てはまる方には、買取を行った当日にご入金が可能です。 ぜひお電話からお気軽にお問い合わせください! ※下記画像をタップするとお電話がかかります。 買取までの流れ WEBフォームからお問い合わせしたい方は下の画像をタップ!

旧車専門店オーナーが伝えたい「旧車購入の5つの落とし穴」とは?
筆者は25年前、1998年からフェアレディZ、Z32専門店を営んでいます。 気づけばZ32もすっかり旧車になってしまいました。 それら平成初期のクルマは一時期人気がガタ落ちしましたが、ここ数年で空前の旧車大ブームになっていることはご存知のとおりです。 海外と国内のW需要で、相場が急騰。 R32〜R34型スカイラインGT-Rを筆頭に、信じられない価格になっています。 カーセンサーやグーを見れば憧れのクルマたちがまだ買えるとあって、購入を急ぐ方も多いことでしょう。 いい方は悪いですが、ここだけの話し、そこに「落とし穴」が潜んでいることも事実です。 専門店の私たちからのアドバイスは一言。 『思い込みで旧車を買わないこと』です。 その思い込みは、固定概念や心理から生まれるもので、どのようなものが多いのか下記に挙げてみました。 これから旧車を購入される方々のヒントになればと思います。 ■落とし穴1:販売価格が高いから程度が良いと思い込んでしまう 販売価格が安いクルマは、程度が悪く見えます。 「販売価格が高い=価値が高い」と思い込んでしないがちです。 販売価格と、程度は比例するとはいい切れません。 「販売価格が高い=仕入れが高い」可能性もあるのです。 ■落とし穴2:見た目が良いから程度が良いと思い込んでしまう 見た目が悪いクルマは、程度が悪く見えます。 見た目が良いと、大事にされてきたと思い込んでしまいがちです。 見た目と程度が比例するとはいい切れません。 見た目が良いのは、表面上、そのように見せているからかもしれません。 ■落とし穴3:走行距離が少ないから程度が良いと思い込んでしまう 走行距離が多いクルマは、程度が悪く見えます。 走行距離が少ないと、劣化や傷みが少ないと思い込んでしまいがちです。 走行距離と、程度は比例するとはいい切れません。 走行距離が少ないのは、単に長年動いていなかったかもしれません。 ■落とし穴4:ノーマル車だから程度が良いと思い込んでしまう 改造車やいじったクルマは、程度が悪く見えます。 ノーマル車は、大事にされてきたと思い込んでしまいがちです。 状態と、程度は比例するとはいい切れません。 ノーマル車は、実は元々改造車だったかもしれません。 ■落とし穴5:今買わなければなくなってしまう、もっと高くなると思い込んでしまう タマ数が減ってくると、欲しい欲求が高まります。 「今買わなければなくなってしまう」「今買わなければもっと高くなってしまう」と思い込んでいるからです。 希少性と価値は比例しません。 旧車は、焦って買うものではありません。 どうかこれだけは覚えておいてください。 ・ホームページhttp://www.Z32-Zone.com/ ・Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Fairlady-Z32-Proshop-Zone/286263454768481 ・Instagramhttps://www.instagram.com/Z32_Zone.omura/ ・YouTubehttps://www.youtube.com/user/ZoneZ32 [ライター・撮影/小村英樹(Zone代表)]
