「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
旧車の売買と鑑定市場

クルマを売却したのに入金されない!主な原因や対応方法などを紹介
クルマを売却したものの、入金がされず不安を感じている人もいるでしょう。入金されない原因として、業者側の手続きによる遅延やミスなどが挙げられます。 入金されないまま連絡が取れなくなるケースもあるため、なるべく早く対処しなければなりません。この記事では、クルマ売却後に入金されない主な原因や対応方法などを紹介します。 クルマ売却後の一般的な入金タイミング クルマの売却後は、一般的に1週間程度で入金されます。 業者はクルマの状態確認や名義変更手続きなどを行う必要があるため、引渡した当日に売却金を受け取れる わけではありません。たとえば、大手の業者では下記のスケジュールで入金されます。 買取業者 入金タイミングの目安 カーセブン 3営業日以内 ネクステージ 2~3日後 ガリバー 3~4営業日以内 また、土日や祝日を挟む場合や繁忙期では手続きが遅れるケースもあります。安全に取引を進めるためにも、事前に入金予定日を明確にするとよいでしょう。 クルマ売却から入金までの流れ クルマ売却後の一般的な入金のタイミングを把握し、適切な対応がとれるようにしましょう。ここでは、クルマ売却から入金までの流れを紹介します。 1.査定を受ける まずは、買取業者で査定を受けます。 来店数が多い業者の場合は長時間待つ可能性があるため、事前予約をするとよいでしょう。査定の予約は、買取業者の公式サイトや電話でできます。 査定額は業者によって異なります。複数社に依頼すると、買取相場を把握できるうえに、より高く売却できる業者を選べます。 たとえば3社に査定を依頼した場合、下記のように若干の金額差が生じることが通常です。 ・A社 80万円・B社 78万円・C社 83万円 また、売却予定のクルマの買取に特化していたり、買取を強化していたりする業者であれば、より高く売却できるでしょう。 なお、一部ではありますが強引な営業や入金遅延・未入金などのトラブルを引き起こす悪質な業者も存在します。トラブルを避けるためにも、下記に加入している業者に売却することをおすすめします。 ・JAAI(一般財団法人日本自動車査定協会)・JPUC(日本自動車購入協会) 2.必要書類を揃えておく 提示された査定金額に納得し、売却を決めたら必要書類を揃えて業者に提出します。クルマの売却時に必要な書類は、下記のとおりです。 1.印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内2.実印 ※軽自動車の場合は認印3.譲渡証明書4.委任状5.自動車税納税証明書6.車検証7.自賠責保険証明書8.リサイクル券9.住民票 ※発行から3ヶ月以内・車検証の住所から変更がある場合 軽自動車の場合、印鑑証明書と実印が不要です。 また、譲渡証明書と委任状は業者で用意してくれるケースがあります。運輸支局の公式サイトでもひな形をダウンロードできるため、自分に合った方法で各書類を揃えましょう。 ▼関連記事はこちらクルマの売却時に必要な書類は?普通車・軽自動車に分けて解説 3.契約を締結する 必要書類を提出したら、業者との契約を締結します。売却先が悪徳業者の場合、当初の内容と異なる条件を提示するケースもあるため、契約を締結する前は下記を必ず確認してください。 ・買取金額・クルマの引渡し日や方法・入金日 また、契約は口頭で話してた内容ではなく、契約締結時に取り決めた内容が正式なものとして適用されます。たとえば、口頭では80万円と伝えられていても、契約書に70万円と記載されている場合は後者の買取金額が入金されます。 トラブルを避けるためにも契約書に不明点がある場合は、業者にしっかりと説明を求め、納得してから契約を進めましょう。 4.クルマを引き渡す 契約を締結したら指定日にクルマを引き渡します。クルマの引き渡し方法には、下記の3パターンがあり自分に合った方法を選べます。 ・契約締結後に引き渡す・指定日に引き取りに来てもらう・指定日に業者へ持ち込む たとえば、クルマを乗り換える場合、契約締結後ではなく納車日を引渡し日に指定した方がよいでしょう。 ただし、契約締結から引き渡し日までの期間が長いと、その分入金が遅くなる可能性があります。すぐに入金して欲しい場合は、契約締結後にクルマを引き渡すことをおすすめします。 5.入金される クルマを引き渡してから、1週間程度で買取金額が入金されます。早ければ1〜2営業日程度で入金されるケースもあります。 指定された日に入金されなかったり、金額が異なっていたりする場合は、すぐに業者に連絡し状況を確認しましょう。 なお、クルマを引き渡しても必要書類に不備があると、入金のタイミングが遅れるケースもあります。必要書類を提出する際は、漏れがないようにしましょう。 クルマ売却後に入金されない主な原因 クルマ売却後に入金されない主な原因として、手続きの遅延や口座の誤入力などが挙げられます。売却先が悪徳業者だった場合、業者の倒産や夜逃げなども考えられるでしょう。 ここでは、クルマ売却後に入金されない主な原因を紹介します。 手続きの遅延 業者の手続きの遅延により、入金されない可能性があります。 クルマの売却手続きは、基本的に業者側が必要書類を作成し、運輸支局で名義変更を行います。クルマの所有者が変更されない限り、正式なクルマの売却手続きは完了しません。 特に、繁忙期の3月や9月は業務量が多いため処理が遅くなるケースがあるでしょう。また、振り込み手続きを忘れていたり日付を間違えていたりする可能性もあります。 手続きの遅延により入金されない場合、問い合わせるとすぐに対応してくれることもあるため、まずは業者に連絡してみてください。 業者の倒産・夜逃げ 業者と連絡がつかない場合は、業者の倒産により入金されないケースがあります。 個人経営や中小規模の業者でまれにあり、実際に国民生活センターに相談が寄せられているため、可能性はゼロではありません。また、悪質業者の中には、クルマを引き渡した後に夜逃げするケースもあるでしょう。 倒産しても支払い能力がある場合は、買取金額の一部が入金される可能性があります。ただし、話し合いの結果により「売却金の一部だけ」または「1円も支払われない」可能性があることにも留意してください。 倒産や夜逃げといったリスクを避けるためにも、クルマを売却する際は評判や運営実績を事前に調べて、JAAIやJPUCに加入している業者を選びましょう。 口座情報の誤入力 業者側の口座情報の誤入力により、入金されないケースがあります。 振込先を間違えた場合、返金してもらうには「組戻し手続き」を業者側が行わなければなりません。組戻し手続きとは、受取人の口座から振込人の口座に返金する手続きのことです。 振り込んだお金は戻るものの、受取人の出金許可が必要なため、返金されるまで時間を要します。資金繰りが厳しい業者に売却した場合は、組戻し手続きを行った後に振り込むことになるため、売却金が入金されるまで時間がかかるでしょう。 振込先の口座が存在しない場合は入金処理されないため、1営業日程度で振込人の口座に返金されます。自分が教えた口座情報が間違っている可能性もあるため、契約書に記載されている内容を確認してみてください。 最初から入金する気がない 一部の悪質な業者は、売却金を最初から入金する気がないケースもあります。実際に、国民生活センターへ、下記のような相談が寄せられています。 3カ月前に中古車を売ろうと思い、インターネットで一括査定を申し込んだ。複数社に見に来てもらい、買取金額を一番高く提示した事業者と契約した。車を引き渡し、約200万円の代金は1カ月後に銀行口座へ振り込むと説明を受けた。しかし振込予定日の直前に振込日延期の電話があり、その後も「少し臨時休業する。来週営業再開したら振り込む」と言われたり、「金融機関からの融資が下りたら振り込む。今週末また連絡する」と言われたりして延期が続き、一向に振り込まれない。約束通りに支払ってほしい。 引用:国民生活センター「クルマを売る際は要注意!中古車の売却トラブル」 上記のようなケースでは、契約締結時に曖昧な説明をし、入金日を引き延ばす手口を用いて最終的には連絡が取れなくなる傾向があります。 業者に対して不安に思うことがある場合は「入金されるまでクルマや必要書類を引き渡さない」といった条件で契約を交わせるかどうか、事前に相談してみてください。 クルマ売却で入金されないときの注意点 クルマ売却で入金されない場合、契約内容をしっかり確認し、契約解除や減額といった不当な要求に応じないようにしましょう。少しでも不安に感じたら、消費生活センターに相談することも検討してみてください。 ここでは、クルマ売却で入金されないときの注意点を紹介します。 契約解除や減額に応じないようにする 業者からの契約解除や減額に応じないようにしましょう。業者の中には、クルマの引き渡し後に「傷が見つかった」「事故歴を見落としていた」などと理由をつけて、契約解除や減額を求めてくる場合があります。 たとえば、「査定時にはわからなかったが、事故歴があることが判明したため、契約を解除するか30万円の減額に応じてほしい」といった主張をします。 一度合意した契約を不当に変更するのは違法な行為のため、契約時の内容を守るように強く主張し、契約解除や減額には応じないようにしましょう。 事前に契約書を十分に読み込む クルマの売却はクーリング・オフの対象外であり、容易に契約を解除できないため、事前に契約書のキャンセルポリシーを十分に読み込みましょう。クーリング・オフとは、特定の取引において一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。 契約書にキャンセルについての記載があり、条件をクリアすれば契約を解除できるため、他の業者にクルマを売却できます。ただし、キャンセル料が発生する可能性が高いことに留意してください。 少しでも不安を感じたら消費生活センターに相談する 契約後や業者とのやり取りで少しでも不安を感じた場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。消費生活センターでは、クルマの売却トラブルの事例を多く扱っており、適切なアドバイスを受けられます。 早めの相談が解決への第一歩になるため、不安を感じたら遠慮せずに相談しましょう。 クルマ売却で入金されないときの対応方法 逃げ得を防ぐためにも、クルマ売却の入金トラブルは早めに対処する必要があります。適切な対応方法を把握し、スムーズに解決しましょう。 ここでは、クルマ売却で入金されないときの対応方法を紹介します。 1.まずは業者に連絡を取る クルマを売却したにもかかわらず、入金確認ができない場合はまず業者に連絡を取り、遅れている理由を確認しましょう。単なる手続きの遅延や、振込情報の誤入力が原因であれば、すぐに解決できます。 連絡する際は、契約書や査定時の書類を手元に準備し、具体的な支払い期日を再確認しておきましょう。業者の対応が不誠実だったり、明確な支払い予定を示してもらえなかったりする場合は、次のステップに進みましょう。 2.消費生活センターなどに相談する 明確な支払い予定を示してくれなかったり、業者と連絡が取れなかったりする場合は、消費生活センターに相談しましょう。消費生活センターでは、クルマの売却トラブルに関する相談を受け付けており、適切なアドバイスを提供してくれます。 また「JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)」でも、買取トラブルの相談窓口を設けています。JPUCは適正な取引を推進する団体であり、加盟業者であれば指導や対応を求めることが可能です。JPUC公式サイトで相談窓口をチェックし、入金されない旨を伝えてみてください。 3.弁護士に相談する 連絡がつかなくなった場合は、弁護士に相談して法的措置を取ることも検討してみてください。弁護士に相談し法的措置を取れば、法的な圧力をかけられるため、業者に入金を促すことが可能です。 特に、少額訴訟や損害賠償請求を視野に入れる場合は相談するとよいでしょう。 また、法テラスでは一定の条件を満たす場合に無料で法律相談ができるほか、弁護士費用の立て替え制度を利用できるケースがあります。法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。 経済的な状況により弁護士費用を用意できない場合は、法テラスを利用しましょう。 クルマ売却の入金トラブルの対策 クルマ売却の入金トラブルを防ぐには、信頼できる業者を選び必要書類や口座情報の誤りに注意する必要があります。 続いて、クルマ売却の入金トラブルの対策を紹介します。 信頼できる業者を選ぶ クルマ売却の入金トラブルを防ぐには、信頼できる業者を選ぶ必要があります。信頼できる業者を見極めるには、まず法人かどうかを確認しましょう。法人は、一定のルールに基づいて営業しているため、トラブルのリスクが低い傾向にあります。 買取実績や評判も判断材料の1つです。口コミサイトやレビューをチェックし、過去に入金トラブルがないかを調べましょう。 また、担当スタッフの対応からも信頼性が読み取れます。誠実で丁寧な説明をしてくれるスタッフがいる業者は、契約内容や入金対応などをしっかり行ってくれる可能性が高いでしょう。 加えて、JPUC(日本自動車購入協会)やJAAI(日本自動車査定協会)に加盟しているかどうかもチェックしてみてください。加盟店は、消費者を守るために厳格なルールを守ることが義務付けられているため、信頼できる業者の判断材料となるでしょう。 必要書類や口座情報の誤りに注意する クルマ売却の入金トラブルを防ぐには、必要書類や口座情報の誤りに注意しましょう。 必要書類の不備は、手続きが滞り入金が遅れる原因です。事前に業者から必要書類のリストをもらい、漏れがないか確認しましょう。 また、銀行名や支店名、口座番号に誤りがあると入金が遅れます。契約書に口座情報を記入する際は、内容を再確認するとともに業者とダブルチェックをしましょう。 まとめ 買取金額はクルマを売却してから、1週間程度で入金されます。ただし、手続きの遅延やミスにより、クルマを売却したにもかかわらず入金されないケースがあります。 業者によっては契約解除や減額を要求されたり、最悪の場合は入金がされないまま連絡が取れなくなったりする事例もあります。入金されないトラブルが発生した際は、業者へ早めに連絡を取り、必要に応じて消費生活センターや弁護士に相談することも検討しましょう。

クルマの売却に印鑑証明が2通必要な理由とは?発行方法まで解説
初めてクルマを売却する方の中には、なぜ印鑑証明書が2通必要なのか疑問に思われている方もいるでしょう。売却したい気持ちとは裏腹に、手続きの面倒さはできるだけ避けたいものです。 本記事では、クルマの売却に印鑑証明書が2通必要な理由をはじめ、発行方法や必要書類までをまとめてお伝えします。 【普通車】クルマ売却で印鑑証明書が2通必要な理由 クルマの売却には印鑑証明書が2通必要です。これは、印鑑証明書が実印の有効性を示すものであり、売却手続きでは実印を押印する書類が2通あるためです。それでは、クルマ売却における印鑑証明書の用途について、詳しくみていきましょう。 譲渡証明書に添付する 譲渡証明書は、クルマの所有権を買取業者に正式に移転するための証明書です。国土交通省においても、譲渡証明書に実印を押印する旨が説明されています。 参考:国土交通省「譲渡証明書の記載方法」 委任状(名義変更手続き)に添付する 買取業者に名義変更の手続きをお願いする場合、委任状が必要です。譲渡証明書と同様に、実印の押印と印鑑証明書を添付します。 軽自動車のクルマ売却で印鑑証明書は不要 軽自動車のクルマを売却する場合、普通車とは異なり印鑑証明書の準備は不要です。実印と印鑑証明書は資産の移動において必要なものであり、軽自動車は法律上「資産」と扱われません。 さらに、譲渡証明書や委任状も不要で、契約書への押印も認印で対応できます。なお、所有者権解除のような特殊な手続きの場合、印鑑証明書を求められる可能性があります。該当する方は、買取業者に確認しておくと安心です。 クルマ売却の前に印鑑登録が必要 クルマの売却前に印鑑登録が必要なのは、実印で進める手続きがあるためです。直前になって慌てないために、印鑑登録の手順を確認しておきましょう。 必要なもの 印鑑登録の手続きに必要なものは、以下のとおりです。 ・登録する印鑑:実印として使用予定のもの・本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど・手数料:自治体によって異なる(東京都北区の場合、1件300円) 出典:北区役所「印鑑証明を取るとき、何が必要ですか」 登録可能な印鑑の条件 登録可能な印鑑の条件は、以下のとおりです。 ・住民票に登録されている氏名が記載されていること(旧氏を住民票に記載している場合は、旧氏での登録も可能)・印影のサイズは直径が8mm~25mmに収まるもの・印鑑の形状は円形、角形、楕円形のいずれか・印影は輪郭が欠けておらず、印影が鮮明であること・材質は変形しにくい素材 以下に当てはまる場合、登録できないため注意しましょう。 ・一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの・ゴム印やその他印材が変形しやすいもの・職業や資格などを表しているもの・文字を極端に図案化したもの・くずし字等で判読が難しいもの・逆彫り(文字が白く浮き出る)してあるもの・指輪の印、印鑑の輪郭内に竜紋や唐草模様などを付したもの・他の人が既に登録している印鑑 出典:北区役所「印鑑登録の手続き」 印鑑証明書の発行方法 ここからは、クルマの売却前に済ませておきたい印鑑証明書の発行方法を紹介します。 役所窓口 印鑑証明書は、本人または代理人でも取得できます。必要なものが本人と代理人で以下のように異なります。 手続きする人 必要なもの 本人 ・印鑑登録証(カード)・マイナンバーカード・手数料 代理人 ・印鑑登録証(カード)・本人確認書類・手数料 原則として委任状は不要です。ただし、自治体によっては委任状の提出を求められる場合があるため、事前に役所へ確認しておくと安心です。 手続きの流れも本人と代理人で異なるため、確認しておきましょう。 手続きする人 手続きの流れ 本人 1.役所の窓口で印鑑登録証明書交付申請書を入手し、必要事項を記入して提出する2.印鑑登録証(カード)を利用する場合は、暗証番号を入力する3.窓口で印鑑証明書が発行される 代理人 1.役所の窓口で印鑑登録証明書交付申請書を入手し、必要事項を記入して提出する(代理人の記入欄も正確に記入する)2.窓口で印鑑証明書が発行される なお、市区町村によって手続きが異なる場合があるため、事前に管轄の役所に確認しておきましょう。 コンビニ 本人が印鑑証明書を取得する場合、マイナンバーカードを利用すればコンビニでも入手できます。 手続きの流れは、以下のとおりです。 1.コンビニのマルチコピー機にマイナンバーカードをかざす2.画面の案内に従って操作し、暗証番号を入力する3.手数料を支払い、印鑑証明書を受け取る なお、前提として、コンビニ交付に対応している市区町村でなければ発行できません。また、コンビニ発行の受付時間は6時30分~23時です。に限定されています。 参考:コンビニ交付 印鑑証明書の有効期限は3ヶ月 クルマの売却手続きでは、発行から3ヶ月以内のものが必要です。 買取業者によっては、1~2週間程度しか有効期間が残っていない印鑑証明書は受け付けないケースがあるため注意が必要です。 クルマの売却手続きをスムーズに進めるために、印鑑証明書は手続き直前に取得するのが望ましいでしょう。 クルマ売却の必要書類 普通車の売却で必要な書類は、以下のとおりです。 書類名 発行方法・作成方法 備考 自動車検査証(車検証) 運輸支局や自動車検査登録事務所(運輸支局等) 現住所、氏名の確認 印鑑証明書 ・管轄の役所・コンビニ 発行後3ヶ月以内のもの 実印 自動車納税証明書 最寄りの県税事務所 有効期限の確認 自賠責保険証 保険会社 リサイクル券 自動車リサイクルシステム 再発行不可。紛失した場合は自動車リサイクルシステムにて「自動車リサイクル料金の預託状況」を取得・印刷して代用 譲渡証明書 ・買取業者が用意・国土交通省のWebサイト 委任状 ・買取業者が用意・国土交通省のWebサイト 軽自動車の売却で必要な書類は、以下のとおりです。 書類名 発行方法・作成方法 備考 軽自動車検査証 軽自動車検査協会 現住所、氏名の確認 認印 軽自動車納税証明書 管轄の役所 有効期限の確認 自賠責保険証 保険会社 リサイクル券 自動車リサイクルシステム 再発行不可。紛失した場合は自動車リサイクルシステムにて「自動車リサイクル料金の預託状況」を取得・印刷して代用 まとめ クルマを売却する際、普通車と軽自動車で必要な書類が異なります。普通車の場合、2通の印鑑証明書が必要です。発行から3ヶ月以内のものが有効であるため、売却するタイミングに合わせて用意しましょう。 なお、軽自動車の場合、印鑑証明書は原則不要です。ただし、所有権解除のような特殊なケースが提出を求められる場合もあるため、買取業者に確認するとよいでしょう。 発行の手続きは本人と代理人で異なります。紹介した方法を参考に準備を進めてください。
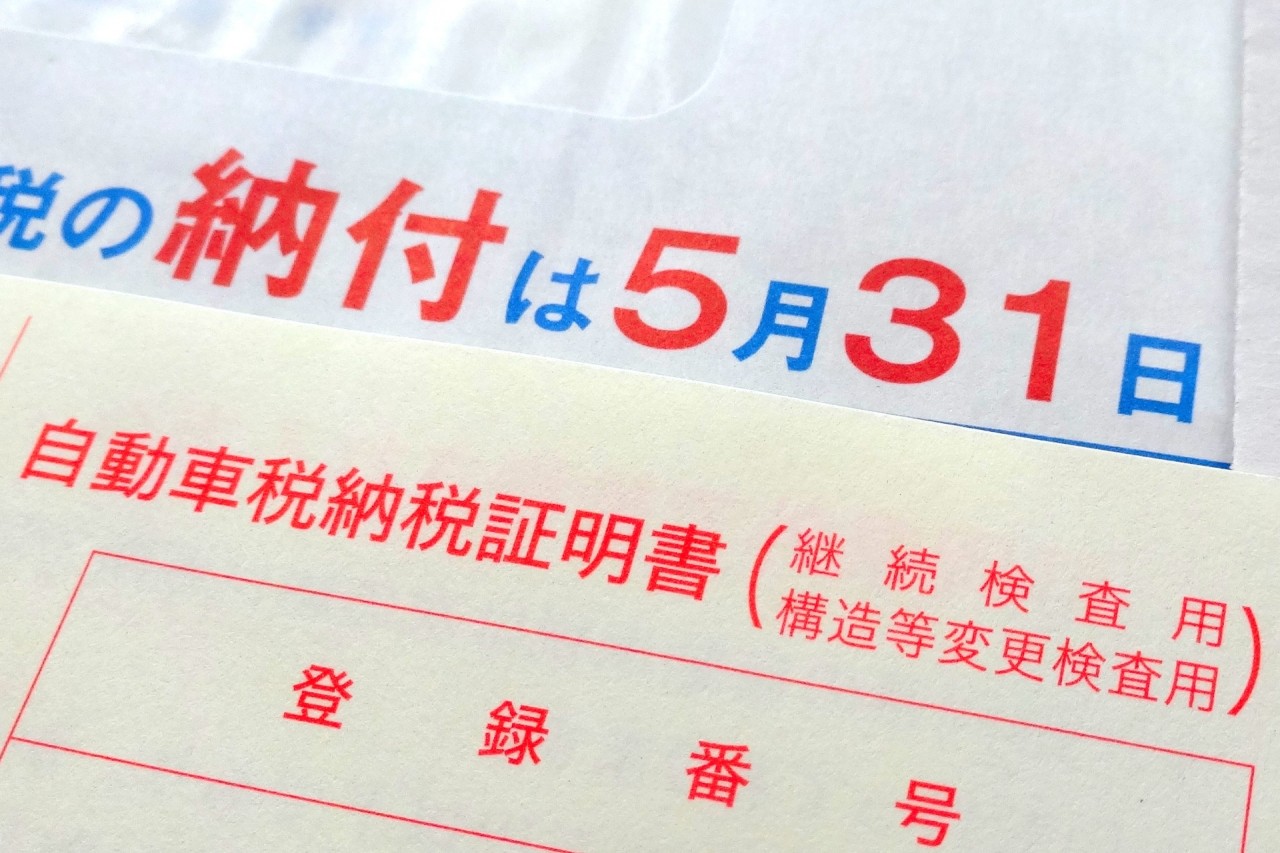
クルマの売却に納税証明書が必要な理由とは?PayPayの対応も解説
クルマの売却時には、自動車税の未納確認や車検時の手続き、ローン完済時の所有権解除など、さまざまな理由で納税証明書が必要です。 PayPayなどのキャッシュレス決済で自動車税を納付した場合、納税証明書の発行に時間がかかるケースがあるため注意が必要です。 本記事では、クルマ売却時に納税証明書が求められる理由や、キャッシュレス決済時の対応方法について詳しく解説します。 クルマの売却時に納税証明書が必要な理由 クルマを売却する際に納税証明書が必要な理由は、自動車税の未経過分や車検時の納税の確認、ローン完済時の所有権解除手続きに必要なためです。それぞれの場面で、納税証明書がどのように利用されるのか詳しくみていきましょう。 自動車税の未経過分を確認するため クルマの買取額には、毎年6月に納付する自動車税の未経過分(最大約5万円)が含まれる場合があります。買取店は、支払い状況を確認し適切な買取価格を算出するために、納税証明書で未経過分を確認します。 なお、納税証明書がなくても自動車税の納付が確認できればよいため、コンビニ支払いの領収書やオンライン納付の画面でも対応可能です。 次の持ち主が車検を受ける際に必要 自動車税が未納の場合、車検を受けられません。通常、運輸局は納税状況を確認できるため、納税証明書の提出は不要です。 ただし、PayPayなどキャッシュレス決済で納付した場合は、情報の反映に3週間程度かかります。車検のタイミングと重なった際は、紙の納税証明書を用意しましょう。 所有権解除に必要 ディーラーやローン会社が所有者となっているクルマを売却する場合、所有権解除の手続きが必要です。この手続きは納税証明書の原本がないと行えません。 カードやアプリ決済の場合は納税証明書の再発行が必要 キャッシュレス決済で自動車税を納付した場合、納税証明書は自動発行されないため、再発行手続きが必要です。 自治体は原則として納税証明書の提示を求めており、車検や売却時には納付確認の証明が必須です。 急いで証明書が必要な場合は、金融機関やコンビニでの納付をおすすめします。 納税証明書の再発行の方法 納税証明書の再発行は、車種によって申請窓口が異なります。また、窓口申請と郵送申請でも違いがあります。それぞれの必要書類や注意点について詳しく解説します。 普通車 普通自動車の納税証明書は、都道府県税事務所で再発行できます。申請方法に応じて、必要書類や費用が下記のように異なります。 申請方法 必要書類 費用 窓口 ・納税証明書交付申請書・身分証明書 手数料400円 郵送 納税証明書交付申請書(都道府県HPからダウンロード) ・定額小為替400円・返信用封筒代・切手代 【申請時の注意点】・車検用と一般用の納税証明書があり、売却時には一般用が必要・ナンバーの登録地の都道府県内であれば、どの税事務所でも発行可能・税務署では発行していないため、都道府県税事務所へ申請する 軽自動車 軽自動車の納税証明書は、市区町村役場で再発行できます。普通車とは申請場所と手数料が異なります。申請方法ごとの必要書類や費用は下記のとおりです。 申請方法 必要書類 費用 窓口 ・納税証明書交付申請書・身分証明書 手数料200円 郵送 納税証明書交付申請書(市区町村に要問い合わせ) ・定額小為替(市区町村により異なる)・返信用封筒代・切手代 【申請時の注意点】・市区町村により申請書の様式が異なるため、事前確認が必要・普通車は県税事務所、軽自動車は市区町村役場と窓口が異なる・郵送申請の手数料は自治体により異なるため、必ず確認が必要 自動車税をPayPayで納付するメリット 自動車税をPayPayで納付するメリットについて詳しくみていきましょう。 24時間いつでも納付できる スマートフォンと納税通知書があれば、深夜でも休日でも自動車税を納付できます。コンビニや金融機関に行く必要がないため、仕事や家事で忙しい方にとって便利です。 たとえば、納付期限が翌日に迫っている場合でも、23時59分まで納付が可能です。なお、金融機関ごとに定期メンテナンスが入ります。納付期限直前の深夜に納付する場合は、メンテナンス時間に注意しましょう。 手数料が不要 PayPayでの自動車税納付は手数料0円です。クレジットカードは課税額によって手数料が99円から495円まで段階的に設定されています。排気量の大きなクルマの自動車税は、PayPayのほうがお得です。 出典:国税庁「クレジットカード納付の手続」 PayPayステップのカウント対象 PayPayステップは、月間の利用実績に応じて翌月のポイント還元率が上がる制度です。自動車税の納付も、ステップアップの条件「月間決済回数」と「月間利用金額」にカウントされます。 たとえば、200円以上の決済回数が30回以上+PayPayやPayPayカード、PayPayカードゴールドの合計月間利用金額が10万円以上でポイント付与率がアップします。仮に自動車税が年額5万円程度だとすると、残り5万円程度を生活費や趣味の費用などで利用することで条件を達成できます。 ただし、2022年4月からは税金の支払いに対するポイント付与は廃止されており、PayPay残高が増えることはありません。 自動車税をPayPayで納付するデメリット PayPayでの納付は便利な一方で、注意すべき点もあります。以下のデメリットを確認したうえで納付方法を選びましょう。 納税証明書が発行されない PayPayでの納付では、納税証明書は発行されません。以下のような方は、コンビニや銀行窓口での納付をおすすめします。 ・クルマの売却を予定している方・ローン完済による名義変更が必要な方・納税証明書を急いで必要とする方・平日の日中に税事務所へ行く時間が取れない方 コンビニや銀行窓口で納付すれば、その場で納税証明書を受け取れます。一部の地域ではPayPay納付でも後日納税証明書が送付されますが、確実に必要な場合は窓口での納付が安心です。 納付後に即日での車検が受けられない PayPayで納付した場合、納付情報が運輸支局のシステムに反映されるまで最大3週間かかります。そのため、早く車検を受けたい場合はPayPay納付の場合は納税証明書の再発行が必要です。以下のケースでは窓口での納付がおすすめです。 ・納付後1週間以内に車検を予定している場合・車検の期限が迫っている場合・継続検査の予約をすでに取っている場合 納税証明書があれば即日で車検を受けられます。 まとめ PayPayでの納付は窓口の受付時間以外でも可能で、手数料も不要で便利です。しかし、クルマの売却や車検を予定している場合は、納税証明書がその場で受け取れるコンビニや銀行窓口での納付のほうが適しています。 PayPayで納付を済ませている場合は、都道府県税事務所や市区町村役場での再発行手続きを忘れずに行いましょう。

2025年11月にマツダ トリビュートが25年ルール解禁!今後値上がりする?
マツダ トリビュートが2025年11月に25年ルール解禁を迎えます。フォードとの共同開発で誕生したこのSUVは、アメリカ市場でも人気を博したモデルです。日本では比較的珍しい存在であることから、25年ルール解禁により価値が変動する可能性があります。今回は、トリビュートの魅力と今後の価値について詳しく解説していきます。 2025年11月にマツダ トリビュートが25年ルール解禁! 2025年11月、トリビュートが25年ルールの解禁を迎えます。2000年11月に発売されたトリビュートは、マツダとフォードの共同開発によって生まれた小型クロスオーバーSUVです。発売当時、本格的なオフロード性能と乗用車感覚の取り回しのよさを両立させた先進的なモデルでした。 そもそも25年ルールとは? 25年ルールとは、製造から25年以上が経過した右ハンドル車をアメリカ国内に輸入できる特別な規定です。通常、アメリカでは右ハンドル車の輸入が制限されていますが、このルールにより、25年以上経過したクルマはクラシックカーとして登録が可能となります。さらに、関税や排ガス規制も対象外となるため、日本の旧車をそのままの状態でアメリカに輸入することができるようになります。 ▼詳しくはこちらアメリカ「25年ルール」とは?名車の中古相場が急騰するしくみ 25年ルール解禁でマツダ トリビュートは値上がりする? トリビュートの場合、25年ルール解禁による大幅な価格上昇は限定的である可能性が高いと考えられます。その理由として、すでにアメリカ市場では同型のフォード エスケープが販売されていたことが挙げられます。ただし、マツダ独自のチューニングが施された日本仕様車として、一部のマニアやコレクターからの需要は見込まれるかもしれません。特に良好なコンディションを保った個体や、希少なグレードについては、一定の価値を保持する可能性があります。 25年ルールが解禁されるマツダ トリビュートの魅力 トリビュートの最大の魅力は、本格的なSUVの機能性と、乗用車のような快適な乗り心地を両立させた点にあります。3.0L V6エンジンを搭載したLXグレードでは、最高出力203psと最大トルク27kg・mを発揮し、力強い走りを実現。 室内空間も特筆すべき魅力の1つです。広々としたキャビンは、当時のSUVとしては珍しく乗用車感覚での使用が可能で、ファミリーユースにも適していました。また、リアシートを倒すことで大容量のラゲッジスペースを確保でき、アウトドアやレジャーでの使用にも対応できる実用性を備えています。 マツダ トリビュート以外で2025年に25年ルールが解禁される車種一覧 2025年には、トリビュート以外にも注目の車種が25年ルール解禁を迎えます。代表的な車種は以下の通りです。 ・トヨタ WiLL Vi(1月解禁)クラシックと未来を融合した独創的なデザインをもつモデル。丸みを帯びたボディライン、バブルのようなヘッドライト、円形のリアランプが特徴的で、内装も丸型メーターなど個性的です。 ・トヨタ 2代目 エスティマ(1月解禁)2代目エスティマは、革新的な空力デザインと広々とした3列7〜8人乗りの室内空間を両立させた先進的ミニバンです。2.2Lや3.0Lエンジン、4WDモデルも用意され、実用性と走行性能を高次元で融合したモデルです。 ・トヨタ bB(2月解禁)トヨタ bBは2000年に登場した独特なボックス型デザインが特徴のコンパクトカーです。四角いフォルムと広い室内空間を持ち、カスタマイズ性の高さから若者に人気を集めました。1.3Lと1.5Lエンジンを搭載し、実用性とスタイリッシュさを両立させた革新的なモデルです。 ・ダイハツ アルティス(3月解禁)ダイハツ アルティスは、トヨタ カムリのOEMモデルとして登場した高級セダン。2.2L 直4エンジンによる滑らかな走りと快適な乗り心地、高い信頼性が特徴です。広い室内空間も魅力です。 ・トヨタ 2代目RAV4(5月解禁)2代目RAV4は、初代の成功を発展させたクロスオーバーSUVです。拡大したボディサイズと室内空間を持ちながらも取り回しの良さを維持しています。2.0L/1.8Lエンジンを搭載し、洗練されたデザインと実用性を兼ね備え、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。 ・トヨタ オーパ(5月解禁)オーパは、2000年5月に発売された5ドアハッチバックです。コンパクトなサイズながらも広々とした室内を有し、ファミリー層から人気を博しました。 ・ホンダ アコード ユーロR CL1型(6月解禁)高回転型エンジンH22Aを搭載した高性能セダンで、スポーティな走りが魅力のモデルです。 ・ダイハツ アトレー7(7月解禁)アトレー7は、コンパクトなボディに7人乗りの3列シートを実現した実用的なミニバンです。1.3Lのエンジンを搭載し、スライドドアや折りたたみ可能な後部座席など、日常使いに便利な機能を備えています。 ・スバル インプレッサ WRX STI GDB型(8月解禁)2.0L水平対向ターボエンジンを搭載した4WDスポーツセダンで、圧倒的な走行性能を誇ります。 ・ダイハツ YRV(8月解禁)コンパクトながらも広い室内空間と個性的なデザイン、スポーティな走りを兼ね備えた実用性の高いモデルです。 ・30セルシオ(8月解禁)30セルシオは、2000年8月から製造されたトヨタのフラッグシップ高級セダン。4.3L V8エンジンを搭載し、世界トップレベルの静粛性と快適な乗り心地が特徴です。 ・9代目カローラ(8月解禁)9代目カローラは、2000年から2017年まで製造された大衆車です。空力性能を重視した流麗なデザインと、1.3L、1.5L、1.8Lのエンジンによる力強い走りを両立させています。 ・ホンダ スマートシビック(9月解禁)ホンダ シビックの7代目モデルです。先代よりも一回り以上大きくなったボディで、ミニバンを思わせる外観をもちます。 ・ホンダ 3代目シビックフェリオ(9月解禁)走行性能、実用性、どちらにもこだわってつくられたコンパクトカーです。VTECエンジンを搭載し、小さいボディながらハイパワーを誇ります。 ・トヨタ 110系 マークⅡ(10月解禁)高級感あるセダンフォルムと多彩なパワーユニットが特徴のモデルです。ツアラーVに搭載された1JZ-GTEターボエンジンによる280psの走行性能は多くのファンを魅了しています。 ・トヨタ オリジン(11月解禁)トヨタ生産台数1億台突破を記念して約1,000台のみ製造された限定車です。初代クラウンをモチーフにした豪華セダンとして注目を集めました。 ・日産 エクストレイル(11月解禁)初代エクストレイルは最高280psのエンジンと「ALL MODE 4×4」で本格オフロード性能と日常の使いやすさを両立。スクエアなボディによる大容量荷室と実用的装備、優れた視界と収納で、クロスオーバーSUVの先駆けとして魅力的なモデルです。 ・トヨタ クルーガー(11月解禁)クルーガーは、2000年発売のSUVです。セダンの快適性とSUVの実用性を高次元で融合し、高い走行性能と乗り心地を実現しました。 ・スズキ グランドエスクード(12月解禁)グランドエスクードは、2.7LのV6エンジンと本格的な4WDシステムを搭載した、スズキのSUVです。高い走破性と日常の快適性を両立し、さまざまな路面状況に対応できます。 まとめ 2025年11月に25年ルール解禁を迎えるトリビュートは、フォードとの共同開発により生まれた、本格的なSUVの性能と乗用車感覚の使い勝手のよさを両立させた魅力的なモデルです。 トリビュートを売却する場合、プロの査定員による適切な価値評価が重要です。旧車王では、専門の鑑定士が細部にわたる入念な査定を行い、クルマの価値を最大限に引き出した買取価格をご提示いたします。査定は無料で、日本全国どこでも出張可能なため、お気軽にご相談ください。

2025年10月にホンダ ストリームが25年ルール解禁!今後値上がりする?
2025年10月に、ホンダ ストリームが25年ルール解禁を迎えます。7人乗りながらスポーティな走りを実現したミニバンとして、発売当時から高い評価を得てきたストリームは、25年ルールの解禁によって新たな注目を集める可能性があります。今回は、ストリームの25年ルール解禁の背景と、モデルの魅力について詳しく解説していきます。 2025年10月にホンダ ストリームが25年ルール解禁! 2025年10月、ホンダ 初代ストリームが25年ルール解禁となります。2000年10月に発売された初代ストリームは、「新価値7シーター」というコンセプトのもと開発された7人乗りミニバンです。従来のミニバンにはない低重心のスタイリングと高い運動性能を備え、新しいカテゴリーを確立したモデルとして評価されました。発売からわずか10ヶ月で累計販売台数が10万台を超えたことから、当時の人気ぶりがうかがえます。 そもそも25年ルールとは? 25年ルールとは、アメリカの自動車輸入に関する特別な規定です。製造から25年以上が経過したクルマは、クラシックカーとして登録が可能となり、通常では認められない右ハンドル車の輸入が可能になります。また、関税や排ガス規制も緩和されるため、コレクターやエンスージアストにとって魅力的な制度となっています。このルールにより、2025年10月以降、初代ストリームをアメリカへ輸出できるようになります。 ▼詳しくはこちらアメリカ「25年ルール」とは?名車の中古相場が急騰するしくみ 25年ルール解禁でホンダ ストリームは値上がりする? ストリームの場合、他の人気スポーツモデルと比較すると、急激な価格高騰の可能性は低いと考えられます。これは、ミニバンというカテゴリーの特性上、アメリカでのスポーツカーほどの需要が見込めないためです。しかし、良好なコンディションを保った個体や、特別仕様車などの希少モデルについては、一定の値上がりが期待できる可能性があります。 25年ルールが解禁されるホンダ ストリームの魅力 ストリームの最大の魅力は、ミニバンでありながら優れた走行性能をもつ点です。全長4,550mmながら、低重心設計と適度なホイールベースにより、安定した走りを実現。さらに、ダブルウィッシュボーン式リアサスペンションの採用により、コーナリング性能も高いレベルで確保しています。 パワーユニットは、1.7L直列4気筒SOHCと2.0L直列4気筒DOHCの2種類を用意。特に2.0Lエンジンは最高出力154psを発揮し、ミニバンとは思えない加速性能を実現しました。また、コンパクトなボディサイズながら3列シートを備え、実用性も十分に確保。2列目スライドシートと3列目跳ね上げシートの採用により、多彩なシートアレンジが可能となっています。 ホンダ ストリーム以外で2025年に25年ルールが解禁される車種一覧 2025年には、ストリーム以外にも注目の車種が25年ルール解禁を迎えます。 ・トヨタ WiLL Vi(1月解禁)クラシックと未来を融合した独創的なデザインをもつモデル。丸みを帯びたボディライン、バブルのようなヘッドライト、円形のリアランプが特徴的で、内装も丸型メーターなど個性的です。 ・トヨタ 2代目 エスティマ(1月解禁)2代目エスティマは、革新的な空力デザインと広々とした3列7〜8人乗りの室内空間を両立させた先進的ミニバンです。2.2Lや3.0Lエンジン、4WDモデルも用意され、実用性と走行性能を高次元で融合したモデルです。 ・トヨタ bB(2月解禁)トヨタ bBは2000年に登場した独特なボックス型デザインが特徴のコンパクトカーです。四角いフォルムと広い室内空間を持ち、カスタマイズ性の高さから若者に人気を集めました。1.3Lと1.5Lエンジンを搭載し、実用性とスタイリッシュさを両立させた革新的なモデルです。 ・ダイハツ アルティス(3月解禁)ダイハツ アルティスは、トヨタ カムリのOEMモデルとして登場した高級セダン。2.2L 直4エンジンによる滑らかな走りと快適な乗り心地、高い信頼性が特徴です。広い室内空間も魅力です。 ・トヨタ 2代目RAV4(5月解禁)2代目RAV4は、初代の成功を発展させたクロスオーバーSUVです。拡大したボディサイズと室内空間を持ちながらも取り回しの良さを維持しています。2.0L/1.8Lエンジンを搭載し、洗練されたデザインと実用性を兼ね備え、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。 ・トヨタ オーパ(5月解禁)オーパは、2000年5月に発売された5ドアハッチバックです。コンパクトなサイズながらも広々とした室内を有し、ファミリー層から人気を博しました。 ・ホンダ アコード ユーロR CL1型(6月解禁)高回転型2.2L DOHC VTECエンジンを搭載した高性能セダン。220psの出力と洗練されたハンドリングで、スポーツセダンとして高い評価を受けました。 ・ダイハツ アトレー7(7月解禁)アトレー7は、コンパクトなボディに7人乗りの3列シートを実現した実用的なミニバンです。1.3Lのエンジンを搭載し、スライドドアや折りたたみ可能な後部座席など、日常使いに便利な機能を備えています。 ・スバル インプレッサ WRX STI GDB型(8月解禁)水平対向エンジンと4WDシステムを組み合わせた高性能スポーツセダン。ラリー競技での活躍も相まって、世界中のファンから支持されています。 ・ダイハツ YRV(8月解禁)コンパクトながらも広い室内空間と個性的なデザイン、スポーティな走りを兼ね備えた実用性の高いモデルです。 ・30セルシオ(8月解禁)30セルシオは、2000年8月から製造されたトヨタのフラッグシップ高級セダン。4.3L V8エンジンを搭載し、世界トップレベルの静粛性と快適な乗り心地が特徴です。 ・9代目カローラ(8月解禁)9代目カローラは、2000年から2017年まで製造された大衆車です。空力性能を重視した流麗なデザインと、1.3L、1.5L、1.8Lのエンジンによる力強い走りを両立させています。 ・ホンダ スマートシビック(9月解禁)ホンダ シビックの7代目モデルです。先代よりも一回り以上大きくなったボディで、ミニバンを思わせる外観をもちます。 ・ホンダ 3代目シビックフェリオ(9月解禁)走行性能、実用性、どちらにもこだわってつくられたコンパクトカーです。VTECエンジンを搭載し、小さいボディながらハイパワーを誇ります。 ・トヨタ 110系 マークⅡ(10月解禁)高級感あるセダンフォルムと多彩なパワーユニットが特徴のモデルです。ツアラーVに搭載された1JZ-GTEターボエンジンによる280psの走行性能は多くのファンを魅了しています。 ・トヨタ オリジン(11月解禁)トヨタ生産台数1億台突破を記念して約1,000台のみ製造された限定車です。初代クラウンをモチーフにした豪華セダンとして注目を集めました。 ・トヨタ クルーガー(11月解禁)クルーガーは、2000年発売のSUVです。セダンの快適性とSUVの実用性を高次元で融合し、高い走行性能と乗り心地を実現しました。 ・スズキ グランドエスクード(12月解禁)グランドエスクードは、2.7LのV6エンジンと本格的な4WDシステムを搭載した、スズキのSUVです。高い走破性と日常の快適性を両立し、さまざまな路面状況に対応できます。 まとめ 2025年10月に25年ルール解禁を迎えるホンダ ストリームは、スポーティな走りと実用性を両立した革新的なミニバンとして、自動車史に名を残すモデルです。急激な価格高騰は見込みにくいものの、良好なコンディションを保った個体は、将来的な価値の上昇が期待できるかもしれません。 旧車の価値を最大限に引き出すためには、適切な整備と査定が重要です。弊社・旧車王では、10年以上経過したクルマの買取を専門に行っており、自社工場での修理・修復により、クルマの価値を最大化してご提案いたします。ストリームの売却をご検討の際は、ぜひ旧車王にご相談ください。最短当日、無料で日本全国どこでも出張査定にうかがいます。
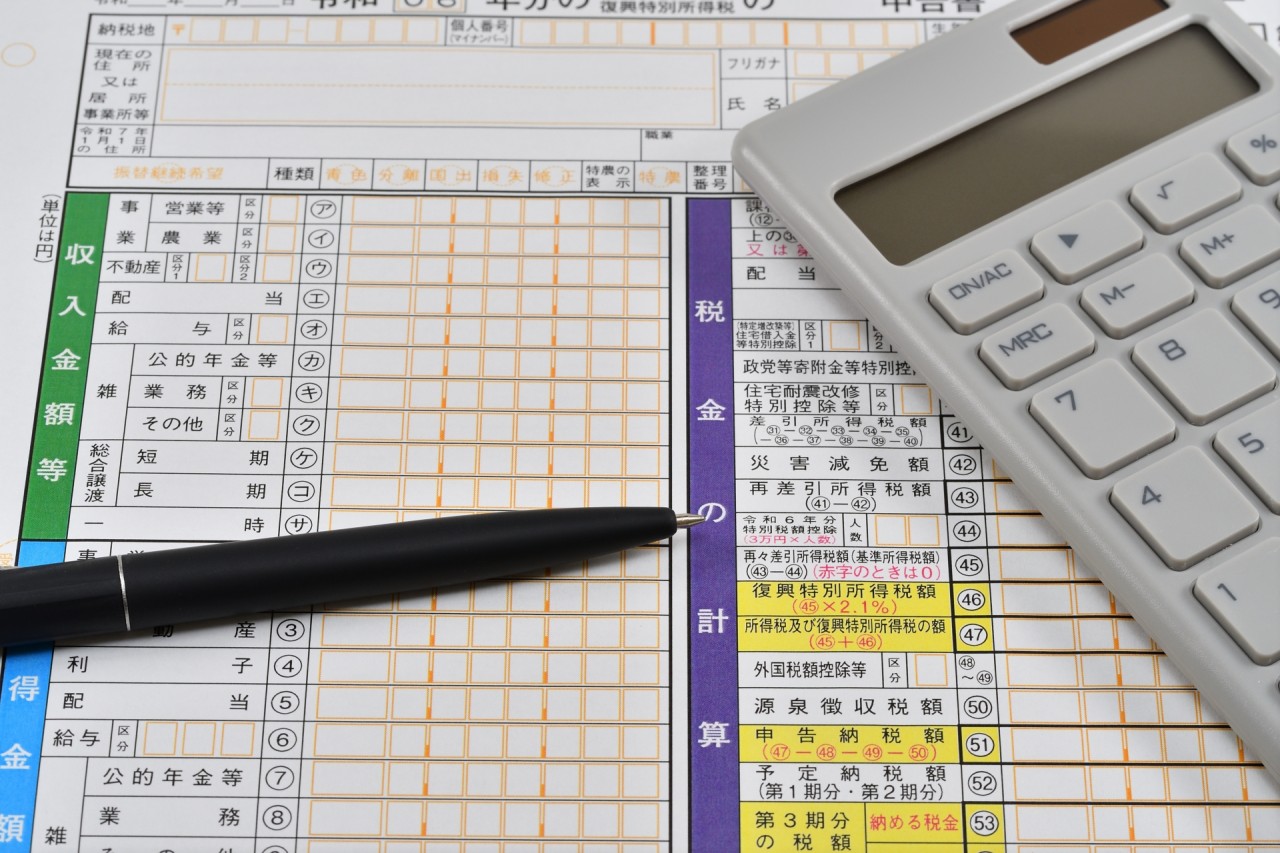
クルマを売却したら確定申告は必要?必要なケースや流れを紹介
クルマを売却し利益が出たものの、確定申告が必要なのか調べている方もいるでしょう。クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。 この記事では、クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケースや不要なケースなどを紹介します。 クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケース クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。譲渡所得とは、資産の売却や譲渡で得た所得のことで、翌年の所得税に影響します。 まずは、クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケースを紹介します。 高級車の売却 高級車を売却すると、確定申告が必要な場合があります。高級車は、日常の移動手段よりも趣味として所有される意味合いが強いため、利益が出れば所得税の課税対象です。 たとえば、売却額が購入額を超えるような高級車を売却した場合が該当します。仮に購入額が300万円で、売却額が500万円の場合は200万円が利益となり、所得税が課税されます。 特に希少価値が高いスポーツカーや旧車などを売却すると、売却額が購入額を超える可能性が高いでしょう。なお、転売目的で高級車を保有し、売却によって利益が出た場合も課税対象になるため確定申告が必要です。 レジャー用のように目的が明確なクルマ レジャー用のように目的が明確なクルマを売却し、利益が出た場合も確定申告が必要です。レジャー用のクルマは、日常使用とは異なり、特定の目的のために購入されることが多いため、譲渡所得の対象として扱われる可能性があります。 たとえば、キャンピングカーといったレジャーで使用するようなクルマです。購入時の目的や使用状況を判断し、適切に対応しましょう。 事業用のクルマ 事業用のクルマの売却で出た利益は、譲渡所得として扱われるため、確定申告が必要です。たとえば、営業車や配送車などといった事業目的で使用しているクルマを売却した場合です。 一方、損失が出た場合にほかの所得と合算すると、所得税の課税対象が減るため節税につながります。 クルマの売却で利益が出ても確定申告が不要なケース 譲渡所得には「50万円」の特別控除があるため、それを超えない限り確定申告は必要ありません。また、日常で必要なクルマを売却し、利益が出た場合も確定申告が不要です。 ここでは、クルマの売却で利益が出ても確定申告が不要なケースを紹介します。 日常生活で使用するクルマ 日常生活で使用するクルマは確定申告が不要です。たとえば、買い物や送り迎えで使っているクルマは対象外です。 ただし、売却額が購入額を大幅に上回った場合は確定申告が必要なケースもあります。日常生活で使用するクルマでも確定申告が必要なケースもあるため、不安に感じた場合は専門家に相談するとよいでしょう。 通勤用のクルマ 通勤や通学で使っているクルマは、売却しても譲渡所得として扱われないため、確定申告が不要です。ただし、売却額によっては日常生活で使用するクルマと同様に確定申告が必要なケースがあることに留意してください。 クルマの売却における譲渡所得の計算方法 譲渡所得には、下記のように2種類あり、それぞれで計算方法が異なります。 種類 定義 計算方法 短期譲渡所得 購入から5年以内で売却 売却額 −(取得費用+譲渡費用)− 特別控除額 長期譲渡所得 購入から5年以上で売却 {売却額−(取得費用+譲渡費用)− 特別控除額}× 1/2 参考:東京地方税理士会「クルマを売却したととき(令和6年5月)」 たとえば、下記の条件で売却した場合の譲渡所得は50万円です。 ・購入から5年以内で売却・売却額 300万円・取得費用 200万円・譲渡費用 0円 ※300万円−200万円−50万円(特別控除額)= 50万円 また、譲渡費用とは売る際にかかった費用のことで、陸送費用や修理費用などが該当します。取得費用はクルマを購入する際にかかった費用で、下記を含む必要があります。 ・車輌本体・付属品・代行費用(車庫証明発行や登録手続きなど)・納車費用 ただし、税金や保険料、リサイクル料金は損金として処理できるため、取得費用に含めるかは任意です。 クルマの売却益が出た際の確定申告の流れ クルマの売却益が出た際に流れを把握しておけば、スムーズに確定申告できます。ここでは、クルマの売却益が出た際の確定申告の流れについて紹介します。 1.売却益が確定申告の対象になるか確認する まずは、売却益が確定申告の対象になるかを確認します。対象の場合は、売却額から取得金額を引いて、売却益の金額を確認しましょう。 なお、事業用としてクルマを所有し、減価償却法を用いて分割で取得金額を計上している場合は、下記の計算式で売却益を確認します。 売却額−帳簿価格(帳簿上のクルマの価値) たとえば、耐用年数6年のクルマを240万円で購入した場合、毎年40万円ずつを計上します。購入から3年目で売却した場合の帳簿価格は120万円です。 2.譲渡所得を計算する 売却益が確定申告の対象であれば、譲渡所得を計算します。譲渡所得は、短期譲渡所得と長期譲渡所得で計算方法が異なるため、間違えないように注意しましょう。 また、車輌本体価格だけでなく付属品や納車費用なども取得費用に含める必要があることに留意してください。 3.必要書類を準備する 譲渡所得を計算したら、確定申告に必要な書類を準備します。クルマの売却益が出た際に必要な書類は下記のとおりです。 ・確定申告書・青色申告決算書(青色申告をする場合)・収支内訳書(白色申告をする場合)・身分証明書・収入を確認できる書類・税金控除の適用を確認できる書類・マイポータルアプリまたはカードリーダー(e-Taxで電子申告する場合)・振込先の銀行口座情報 e-Taxで電子申告する場合、マイナンバーカードをカードリーダーで読み込むため、身分証明書の省略が認められます。また、事前に税務署で本人確認を行い、e-Taxで申請するためのIDとパスワードを付与されている場合も同様です。 e-Taxで確定申告を行う予定がある場合は、カードリーダーの準備、または事前に税務署に出向き電子申告に必要なIDとパスワードを付与してもらいましょう。 4.確定申告書を作成する 必要書類を準備したら、確定申告書を作成します。確定申告書は2枚綴りになっており、収入や所得などをまとめる「第一表」と、詳細を記入する「第二表」があります。 譲渡所得の確定申告では、第一表と第二表に加えて、譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)も作成しなければなりません。 確定申告書の作成は手書きで行えるものの、会計ソフトを使用すれば、よりスムーズに確定申告ができるため必要に応じて使用しましょう。 5.提出・納税 確定申告書を作成したら、下記いずれかの方法で管轄の税務署に提出し、所得税を納税します。 ・直接出向く・郵送・電子申告(e-Tax) 確定申告の期限は、毎年3月15日です(※2024年度分は土日祝に該当するため3月17日まで)。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課せられるため、計画的に確定申告を進めましょう。 まとめ クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。 事業用のクルマを売却した際はもちろん、売却額が購入額を上回る場合も確定申告をしなければなりません。特に高級車や希少価値がある旧車を売却した場合は、購入額を大幅に上回る可能性があることに留意してください。 確定申告する際は、会計ソフトを使うとスムーズに申告を進められます。仕事で忙しかったり、確定申告の方法について不安に思う場合は、専門家に依頼することも検討してみてください。

クルマの減価償却期間中でも売却は可能?仕訳方法や注意点を紹介
事業用で所有しているクルマは、基本的に分割して経費計上する必要があります。しかし、減価償却期間中でも売却できるのか調べている方もいるでしょう。減価償却期間中でも売却は可能なものの、会計処理が複雑なため、事前に理解を深めておく必要があります。 この記事では、クルマを減価償却の途中で売却する際の仕訳方法や注意点などについて紹介します。 クルマの減価償却期間中でも売却は可能 クルマは減価償却期間中でも売却できます。ただし、減価償却期間中のクルマは事業の損益計算に影響があるため、売却時に得た「売却益」や発生した「売却損」を正しく仕訳しなければなりません。 売却益は、帳簿価格(帳簿に記載されているクルマの評価額)を上回った金額で売却した際に得た利益です。一方、売却損は帳簿価格を下回った金額で売却した際に発生した損益です。 減価償却期間中のクルマの帳簿価格を確認し、売却益を得たのか、または売却損が発生したのかをチェックしましょう。 なお、帳簿価格は「取得原価(購入価格 )− 減価償却累計額」で、算出できます。たとえば、耐用年数4年のクルマを100万円で購入し、3年目で売却する際の減価償却累計額は75万円です(各年の減価償却費は25万円)。 続いて、取得原価100万円から減価償却累計額の75万円を引き、帳簿価格を算出します。減価償却期間中のクルマは、会計処理が複雑なことに留意してください。 クルマを減価償却の途中で売却する際の仕訳 クルマを減価償却の途中で売却する際の仕訳は、「個人」と「法人」で異なります。また「税込処理」と「税抜処理」のどちらかを採用しているかによっても異なるため、仕訳方法を確認しておきましょう。 ここでは、クルマを減価償却の途中で売却する際の仕訳について紹介します。 個人 個人の場合は「譲渡所得」として計上し、売却益は「事業主借」、売却損は「事業主貸」で仕訳します。譲渡所得とは、資産を売却や譲渡した際に生じた所得のことで、所得税や翌年の住民税に影響します。 続いて、個人が減価償却期間中のクルマを売却した場合の仕訳について紹介します。 直接法(税込) 直接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【売却益】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 30万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 事業主借 5万円 売却益 合計 30万6,000円 合計 30万6,000円 【売却損】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......20万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 20万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 事業主貸 5万円 売却損 合計 25万6,000円 25万6,000円 直接法(税抜) 直接法(税抜)で仕訳した場合の例を紹介します。 【売却益】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 27万2,728円 車輌運搬具 22万7,273円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 仮受消費税等 2万7,272円 消費税 事業主借 1万8,183円 売却益 合計 27万8,728円 合計 27万8,728円 【売却損】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......20万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 18万1,819円 車輌運搬具 22万7,273円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000 リサイクル預託金 仮受消費税等 1万8,181円 消費税 事業主貸 6万3,635円 売却損 合計 25万1,454円 合計 25万1,454円 税抜処理の場合、売却額の消費税分を「仮受消費税等」として仕訳します。なお、税込と税抜では合計金額が異なるものの、最終的に租税公課で調整するため、課税される税金は同額です。 法人 流れは個人のときと同じものの、法人の場合は「固定資産売却益」または「固定資産売却損」の勘定科目で仕訳します。続いて、法人が減価償却期間中のクルマを売却した場合の仕訳について紹介します。 直接法(税込) 直接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【売却益】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 30万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 固定資産売却益 5万円 売却益 合計 30万6,000円 合計 30万6,000円 【売却損】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......20万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 20万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 固定資産売却損 5万円 売却損 合計 25万6,000円 25万6,000円 直接法(税抜) 直接法(税抜)の場合は、下記のように仕訳します。 【売却益】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 27万2,728円 車輌運搬具 22万7,273円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 仮受消費税等 2万7,272円 消費税 固定資産売却益 1万8,183円 売却益 合計 27万8,728円 合計 27万8,728円 【売却損】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......20万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 18万1,819円 車輌運搬具 22万7,273円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000 リサイクル預託金 仮受消費税等 1万8,181円 消費税 固定資産売却損 6万3,635円 売却損 合計 25万1,454円 合計 25万1,454円 下取りの場合 下取りの場合は、クルマの売却と購入をそれぞれ仕訳します。下取りとは、現在所有しているクルマを売却し、売却金をそのお店で購入するための資金に充てることです。 ただし、クルマの売却と購入の仕訳を合算した方がスムーズな会計処理が可能です。 下記の条件で下取りし、それぞれを合算した場合の仕訳方法を紹介します(※直接法・税込・法人)。 【下取りしたクルマ】・購入費用......100万円・下取り費用......20万円・リサイクル預託金......6,000円・帳簿価格......25万円 【購入したクルマ】・購入金額(車輌本体価格、オプション品)......150万円・法定費用(自動車税や重量税など)......2万5,000円・保険料(自賠責保険、任意保険)......3万円・代行費用(納車や手続きなど)......4万円・リサイクル預託金......1万円 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 車輌運搬具 150万円 普通預金 140万5,000円 購入金額 / 購入金額−下取り価格 支払手数料 4万円 車輌運搬具 25万円 支払手数料 / 帳簿価格(下取り車) 保険料 3万円 預託金 6,000円 保険料 / リサイクル預託金(下取り車) 租税公課 2万5,000円 税金 預託金 1万円 リサイクル預託金 固定資産売却損 5万6,000円 売却損 合計 166万1,000円 合計 166万1,000円 貸方勘定項目の普通預金は、購入費用160万5,000円から下取り費用の20万円を引いています。 ローン残債がある場合 ローン残債があるクルマを売却した場合は、下記のように仕訳します(直接法・税込・法人)。 ・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税)・ローン残債......9万円・ローンの手数料......1万円 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 30万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 リサイクル預託金 6,000円 リサイクル預託金 長期未払金 9万円 普通預金 10万円 ローン残債 / ローン精算 支払利息 1万円 固定資産売却益 5万円 ローンの手数料 合計 40万6,000円 合計 40万6,000円 クルマの減価償却の途中で売却する際の注意点 減価償却期間中のクルマの売却する際、会計処理が複雑なため注意点を把握しておく必要があります。ここでは、クルマの減価償却の途中で売却する際に気をつけるべき点について紹介します。 直説法と間接法を正しく使う クルマの減価償却の途中で売却する際は、直接法と間接法を正しく使う必要があります。自社の会計基準や税務要件に合わせて、適切に仕訳をしましょう。 万が一誤った方法で会計処理すると、税務署から修正申告を求められることに注意が必要です。 なお、直接法と間接法は下記のようにメリットとデメリットが異なります。 種類 概要 メリット デメリット 直接法 減価償却費を差し引いた金額を帳簿に記入 帳簿価格を把握しやすい 固定資産台帳を確認しないと、取得金額と減価償却累計額を把握しにくい 間接法 減価償却費の累計額を借方に記入し、帳簿上で減価償却を行う いくらで取得したのかを把握しやすい 減価償却累計額を差し引かないと、帳簿価格を把握できない 初めて会計処理を行う場合は、自社に合う方法で仕訳をしましょう。 税込と税別について理解する クルマの減価償却の途中でクルマを売却する際、税込と税別について理解してから仕訳をしましょう。基本的には、自社で採用している方法に従って仕訳をします。 初めて会計処理を行う場合は、自社に合う方法を選択しましょう。 なお、税込処理での仕訳は、多くの中小企業や個人事業主が採用しています。正確な損益の把握や消費税額の把握が難しいものの、方法が単純なため会計処理の効率化が可能です。 一方、税抜処理での仕訳は、売上規模が大きい大企業が採用しているケースがほとんどです。会計処理が複雑化するものの、消費税率に変動があった場合にスムーズに対応できるほか、節税につながるケースもあります。 売却益と売却損における仕訳を理解する クルマの減価償却の途中で売却する際は、売却益と売却損における仕訳を理解しましょう。具体的な違いは下記のとおりです。 項目 定義 売却益 クルマの帳簿価格を上回る金額で売却した場合(売却した際に得た利益) 売却損 クルマの帳簿価格を下回る金額で売却した場合(売却した際に発生した損失) リサイクル預託金の仕訳も必要 クルマを売却した場合は、リサイクル預託金の仕訳も必要です。リサイクル預託金とは、廃車する際に必要な費用であり、新車購入時に支払います。 売却の場合は廃車にしないため、売却先からリサイクル預託金が返金されます。リサイクル預託金は非課税のため、売却額とは別で仕訳が必要なことに留意してください。 また、リサイクル預託金は下記で構成されており、情報管理料金は含めずに処理する必要があります。 ・シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金 たとえば、下記の場合は130円を引いた22,510円を帳簿に記載します。 ・シュレッダーダスト料金 1万3,500円・エアバッグ類料金 6,910円・フロン類料金 2,100円・情報管理料金 130円 迷ったときは専門家に相談する 減価償却期間中のクルマ売却の仕訳について迷ったときは、専門家に相談しましょう。仕訳では、例外が発生するケースもあります。 申告内容が間違っていた場合、修正申告をして正しい金額に訂正しなければなりません。二度手間になるため、迷った場合は税理士や会計士に相談してみてください。 減価償却が終わったクルマの売却の仕訳 減価償却が終わったクルマを、20万円で売却した場合の仕訳は下記のとおりです。 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 20万円 車両運搬具 1円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 事業主借 19万9,999円 売却益 合計 20万6,000円 合計 20万6,000円 減価償却が終わったクルマの帳簿価格は1円です。 また、個人事業主がクルマを売却した場合、50万円の特別控除が適用されます。売却益が19万9,999円から50万円を引けるため、譲渡所得は0円となり、所得税は発生しません。 まとめ 減価償却期間中でもクルマは売却できるものの、会計処理が複雑です。下取りに出した際やローン残債がある場合は、さらに会計処理が複雑なことに留意してください。 まずはクルマの帳簿価格をもとに、売却益または売却損を算出し、正確に処理しましょう。修正申告を求められる可能性があるため、会計処理について迷った場合は、必要に応じて税理士や会計士などの専門家に相談することをおすすめします。

5月にクルマを売却すると税金はどうなる?還付の有無や売却時の注意点も解説
5月にクルマを売却する場合、原則として売り手は1年分の自動車税(種別割)を納める必要があります。 しかし、買取業者によっては買取をした翌月以降の自動車税(種別割)を還付してもらえます。クルマを査定に出す際は、買取業者が税金の還付に対応しているかどうかを確認するとよいでしょう。 この記事では、5月にクルマを売却したときの税金に関する取り扱いや高値で売却するポイントなどについて詳しく解説します。 5月にクルマを売却すると自動車税(種別割)が還付される 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点でクルマを所有している人に課せられる税金です。 毎年5月上旬ごろに送付される納付書をもとに1年分を一括で納めます。 税額は、クルマの総排気量に応じて決まります。たとえば、クルマを2019年9月30日以前に購入した場合、総排気量1,000ccは2万9,500円、1,500cc超~2,000cc以下は3万9,500円、2,500cc超~3,000cc以下は5万1,000円です。 月割りでの支払いはできず、年度の途中でクルマを売却しても納めた自動車税(種別割)は戻ってきませんが、買取業者によっては還付してもらえることがあります。 納税後に売却する場合は還付手続きをする 5月にクルマを売却する場合、売り手がすでに1年分の自動車税(種別割)を納めていることがあります。 普通自動車を廃車にする場合は、翌年3月までの自動車税(種別割)を還付してもらえますが、原則として売却は対象外です。 しかし、買取業者の多くは残りの期間に応じた税額分を買取金額に上乗せする形で精算をしてくれます。 すでに自動車税(種別割)を納めている場合は、買取業者の査定金額に自動車税(種別割)の未経過分が含まれているかを確認しましょう。 ただし、軽自動車は廃車にしても自動車税(種別割)は還付されないため、買取時にも精算されないケースがほとんどです。 納税前に売却する場合は業者に納付書を渡す 自動車税(種別割)を納めていない段階で5月にクルマを売却する場合、納付期限までに余裕があると買取業者が代わりに納付してくれることがあります。 買取業者に自動車税(種別割)を納付してもらえるのであれば、買取の際に納付書を提出しましょう。 ただし、すべての買取業者が代わりに納税してくれるわけではないため、事前に確認しておくことをおすすめします。 5月のクルマ売却で還付される税金額 自動車税(種別割)の還付額は、売却の翌月から3月末までの月数分に応じて決まるのが一般的です。計算式は「自動車税(種別割)の税額÷12×未経過分の月数」です。 たとえば、2019年9月30日以前に新規登録した排気量1,300ccの普通自動車を5月に売却するとしましょう。 自動車税(種別割)は3万4,500円です。5月に売却する場合、6月から翌年3月までの10ヶ月分が還付されるため、買取価格に上乗せされる金額は「3万4,500円÷12×10ヶ月=2万8,750円」です。 5月にクルマを売却する時点で自動車税(種別割)を納めておらず、買取業者が代わりに納税する場合、2ヶ月分が買取金額から差し引かれるのが一般的です。 クルマを売却するとリサイクル預託金相当額も戻ってくる リサイクル預託金とは、廃車に必要な処理費用を新車の購入時に前払いする金銭のことです。 クルマを売却するときは、リサイクル預託金が次の所有者に引き継がれます。そのため、売り手は買取業者からリサイクル預託金に相当する金額を支払ってもらえます。 買取の場合は、リサイクル預託金の金額分が査定額に含められるのが一般的です。 リサイクル預託金のやり取りをする際は、購入時に受け取ったリサイクル券が必要なため、売却時に提示できるよう準備しておきましょう。 5月のクルマ売却の注意点 5月にクルマを売却するときは、自動車税(種別割)やリサイクル預託金の他にも以下の点に注意する必要があります 車検直後の売却は自動車重量税の払い損になる 自動車重量税は、クルマの重量に応じて課税される税金です。クルマの新規登録・新規検査や車検の際、車検証に記載された有効期限分の税額を一括で納めます。車検証の有効期限は、新車登録時が3年、それ以降は2年です。 自動車税(種別割)と同様、自動車重量税が還付されるのはクルマを廃車にしたときです。クルマを売却しても原則として自動車重量税は戻ってきません。 車検を受けた直後にクルマを売却すると、自動車重量税が払い戻されずに損をする可能性があります。 買取業者によっては、残りの期間分に応じた自動車重量税を買取金額に上乗せしてくれる場合があります。査定を受けるときは、自動車税(種別割)だけでなく自動車重量税の還付にも対応しているか確認しておくとよいでしょう。 中古車への乗り換えでは還付金相当額が購入額に反映されることも 買取業者によっては、クルマを買い取る際に精算した未経過分の自動車税(種別割)を販売価格に上乗せしていることがあります。 中古車への乗り換えを検討している場合は、販売価格に自動車税(種別割)の還付金相当額が上乗せされていないかを中古車販売店に確認するとよいでしょう。 税金関連の対応は業者によって異なる 買取業者のすべてが自動車税(種別割)の還付に対応しているわけではありません。また、還付金額の計算式や還付方法などは買取業者によって異なる場合があります。 クルマの査定を受けるときは、買取業者に自動車税(種別割)の還付について詳細に確認することをおすすめします。 クルマを高く売りたい場合は5月以外の時期も検討する クルマをより高く売りたい場合は、5月の他にも以下のタイミングを検討するとよいでしょう。 高額査定になりやすい時期 クルマがもっとも高く売れやすいといわれるのは「1〜2月」です。 毎年3〜4月は就職や進学、転職などを背景にクルマの需要が増加する時期です。また、3月に決算期前のセールを開催する業者も少なくありません。 買取業者の多くは、書き入れ時に向けて在庫をそろえようと積極的に買取を行うため、査定額が高くなりやすいのです。 同様の理由で「7〜8月」についてもクルマの査定額が高くなりやすいといわれています。 5月に売却すべき事情がない場合は、より高額な査定が期待できる1〜2月または7〜8月にクルマを査定してもらうとよいでしょう。 モデルチェンジ前に売却する フルモデルチェンジやマイナーチェンジが行われると、型落ちモデルの価格相場は下がる傾向にあります。 乗っているクルマが現行モデルであれば、新しいモデルが発表される前に売却をしたほうが売却価格は高くなるでしょう。 前回のモデルチェンジから数年が経過している場合、次期モデルが発表される前に手放すのも1つの方法です。 走行距離も考慮する 走行距離が長いクルマは、エンジン回りや足回りなどの部品の摩耗が進んでいる可能性が高まるため、査定額は下がりやすくなります。 一般的には「5年・5万km」を超えると査定額が下がり、「10年・10万km」を超えると一気に値が下がるといわれています。 クルマの走行距離が5万kmまたは10万kmに近い場合は、早めに売却するのも1つの方法です。 まとめ クルマを売却する際、すでに納めている自動車税(種別割)の未経過分を買取金額に上乗せされる形で清算してもらえることがあります。 ただし、すべての買取業者が還付に対応しているわけではないため、5月にクルマを売却するときは自動車税(種別割)の取り扱いを事前に確認しておきましょう。 売却したいクルマの年式が古い場合は「旧車王」の利用をご検討ください。旧車に精通したスタッフが専門知識と経験を活かして、愛車を適正に鑑定いたします。買取後に事故歴が発覚しても減額はいたしませんので、安心してご相談ください。

2025年9月に3代目シビックフェリオが25年ルール解禁!今後値上がりする?
ホンダの人気コンパクトセダン、3代目シビックフェリオが2025年9月に25年ルール解禁を迎えます。90年代を代表する名車として知られる3代目シビックフェリオは、VTECエンジンを搭載したスポーティなセダンとして、国内外で高い評価を得てきました。現在、アメリカでの需要の高まりが予想され、中古車相場への影響が注目されています。本記事では、3代目フェリオの魅力と25年ルール解禁による市場への影響について詳しく解説します。 2025年9月に3代目シビックフェリオが25年ルール解禁! 2025年9月、3代目シビックフェリオが、アメリカの25年ルール解禁を迎えます。2000年から2005年にかけて製造された3代目シビックフェリオは、コンパクトセダンとして高く評価されています。 VTECエンジンを搭載したモデルがラインナップされており、VTECテクノロジーによる高回転型エンジンの特性と、軽量ボディによる優れたハンドリング性能で、スポーツドライビングの魅力を手軽に味わえるモデルとして、若いドライバーを中心に支持を集めました。 そもそも25年ルールとは? 25年ルールは、アメリカの自動車輸入規制に関する例外規定です。製造から25年以上が経過したクルマは、クラシックカーとして認定され、通常の輸入規制の対象外となります。これにより、日本の右ハンドル車をそのままアメリカに輸入することが可能になります。 さらに、関税や排ガス規制も緩和されるため、コレクターやJDM(Japanese Domestic Market)ファンにとっては、待望の機会です。3代目フェリオの場合、2025年9月以降、アメリカでの需要が高まることが予想されます。 ▼詳しくはこちらアメリカ「25年ルール」とは?名車の中古相場が急騰するしくみ 25年ルール解禁で3代目シビックフェリオは値上がりする? 3代目シビックフェリオの価格動向については、特にVTEC搭載モデルを中心に、値上がりの可能性が高いと考えられます。その理由として、下記が挙げられます。 アメリカでのホンダ車人気 特にVTECエンジン搭載車は、その高回転型エンジン特性と優れた運動性能から、アメリカのJDMファンの間で高い人気を誇っています。 良好な状態の個体の希少性 生産から25年以上が経過し、コンディションのよい個体が少なくなっていることから、状態の良好な車輌は特に高値で取引される可能性があります。 ただし、グレードや使用状態、走行距離などによって価格は大きく異なることが予想されます。 25年ルールが解禁される3代目シビックフェリオの魅力 3代目シビックフェリオの魅力は、なんといっても革新的なパワートレインです。特にRSグレードに搭載されたD17A型VTECエンジンは、最高出力130ps/6,300rpmを発揮し、当時のコンパクトカーとしては優れた性能を誇りました。 洗練されたデザインも大きな特徴で、前期型のシャープなフロントマスクと流麗なサイドラインにより、スポーティさと上質さを両立させたエクステリアデザインは、現代でも色あせない魅力を放っています。 また、コンパクトなボディサイズながら、広々とした室内空間と使い勝手のよいトランクスペースを確保。日常使いの利便性も高く評価されています。 3代目シビックフェリオ以外で2025年に25年ルールが解禁される車種一覧 2025年には、3代目フェリオ以外にも注目の車種が25年ルール解禁を迎えます。 ・トヨタ WiLL Vi(1月解禁)クラシックと未来を融合した独創的なデザインをもつモデル ・トヨタ 2代目 エスティマ(1月解禁)革新的な空力デザインと広々とした3列7〜8人乗りの室内空間を両立させた先進的ミニバン ・トヨタ bB(2月解禁)トヨタ bBは2000年に登場した独特なボックス型デザインが特徴のコンパクトカー ・ダイハツ アルティス(3月解禁)ダイハツ アルティスは、トヨタ カムリのOEMモデルとして登場した高級セダン ・トヨタ 2代目RAV4(5月解禁)初代の成功を発展させたクロスオーバーSUV ・トヨタ オーパ(5月解禁)コンパクトなサイズながらも広々とした室内を有する5ドアハッチバック ・ホンダ アコード ユーロR CL1型(6月解禁)2.2L DOHC VTECエンジンを搭載した高性能セダン ・ダイハツ アトレー7(7月解禁)コンパクトなボディに7人乗りの3列シートを実現した実用的なミニバン ・スバル インプレッサ WRX STI GDB型(8月解禁)スバルの4WDスポーツセダンの代表格 ・ダイハツ YRV(8月解禁)コンパクトながらも広い室内空間と個性的なデザイン、スポーティな走りを兼ね備えた実用性の高いモデル ・30セルシオ(8月解禁)30セルシオは、2000年8月から製造されたトヨタのフラッグシップ高級セダン ・9代目カローラ(8月解禁)空力性能を重視した流麗なデザインと、1.3L、1.5L、1.8Lのエンジンによる力強い走りを両立させたモデル ・ホンダ スマートシビック(9月解禁)ミニバンを思わせる外観をもつシビックの7代目 ・トヨタ 110系 マークⅡ(10月解禁)高級感あるフォルムと多彩なパワーユニットが魅力のセダン ・トヨタ オリジン(11月解禁)トヨタ生産台数1億台突破を記念して約1,000台のみ製造された限定車 ・マツダ トリビュート(11月解禁)マツダとフォードの共同開発によって生まれた、実用性と優れた走行性能を兼ね備えた小型クロスオーバーSUV ・日産 エクストレイル(11月解禁)スクエアなボディによる大容量荷室と実用的装備、優れた視界と収納で、クロスオーバーSUVの先駆けとして魅力的なモデル ・トヨタ クルーガー(11月解禁)セダンの快適性とSUVの実用性を高次元で融合し、高い走行性能と乗り心地を実現したモデル ・スズキ グランドエスクード(12月解禁)2.7LのV6エンジンと本格的な4WDシステムを搭載した、スズキのSUVで まとめ 2025年9月に25年ルール解禁となる3代目シビックフェリオは、VTECエンジンによる高性能と実用性を兼ね備えた名車として、アメリカ市場での高い需要が期待されます。特に状態の良いVTEC搭載モデルは、コレクターズアイテムとしての価値も高く、今後の価格上昇が予想されます。 3代目シビックフェリオの売却をお考えの方は、旧車王にぜひご相談ください。クルマを熟知した専門スタッフが、お客様の大切なクルマを適正価格で査定させていただきます。最短当日の無料出張査定も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

2025年9月にスマートシビックが25年ルール解禁!今後値上がりする?
ホンダが2000年9月に発売したスマートシビックが、2025年9月にアメリカの25年ルール解禁を迎えます。シビックの7代目として誕生したスマートシビックは、当時から独自の魅力を放つモデルとして注目を集めました。 今回は、スマートシビックの25年ルール解禁に関する情報と、モデルの特徴について詳しく解説していきます。 2025年9月にスマートシビックが25年ルール解禁! 2025年9月、スマートシビックが25年ルール解禁となります。このモデルは、先代までのコンパクトなサイズから一新して、ボディが一回り以上拡大されました。5ドアモデルにはフラットフロアが採用され、外観も然ることながら室内もミニバンを思わせる空間へと進化を遂げています。 実用性と日本車としての信頼性の高さにより、25年ルール解禁後は中古車市場で一定の需要が見込まれます。 そもそも25年ルールとは? 25年ルールとは、製造から25年以上が経過したクルマについて、アメリカへの輸入規制を緩和する特別な制度です。通常、アメリカでは右ハンドル車の輸入が制限されていますが、25年以上経過したクルマはクラシックカーとして登録が可能となります。このルールにより、日本の中古車がアメリカ市場に流通する機会が生まれ、特に人気モデルは価格が上昇する傾向にあります。 ▼詳しくはこちらアメリカ「25年ルール」とは?名車の中古相場が急騰するしくみ 25年ルール解禁でスマートシビックは値上がりする? スマートシビックは、25年ルール解禁後に急激な価格上昇は見込みにくい可能性があります。その理由として、同時期に解禁となるアコードユーロRやインプレッサWRX STiといった高性能スポーツモデルと比較すると、アメリカでの需要が限定的と予想されるためです。 ただし、良好なコンディションを保った個体や低走行距離の個体については、一定の価値を維持する可能性があります。 25年ルールが解禁されるスマートシビックの魅力 スマートシビックの最大の魅力は、クルマとしての実用性と優れた走行性能を両立した点です。 パワートレインには1.5L SOHCエンジンを搭載し、20km/Lの低燃費を実現。最高出力105ps、最大トルク13.8kg-mを発生し、市街地での扱いやすさと高速巡航時の余裕を両立させました。また、シビックの特徴である低重心設計により、安定した走行性能も特徴です。 スマートシビック以外で2025年に25年ルールが解禁された車種一覧 2025年には、以下の注目モデルが25年ルール解禁を迎えます。・トヨタ WiLL Vi(1月解禁)クラシックと未来を融合した独創的なデザインをもつモデル。丸みを帯びたボディライン、バブルのようなヘッドライト、円形のリアランプが特徴的で、内装も丸型メーターなど個性的です。 ・トヨタ 2代目 エスティマ(1月解禁)2代目エスティマは、革新的な空力デザインと広々とした3列7〜8人乗りの室内空間を両立させた先進的ミニバンです。2.2Lや3.0Lエンジン、4WDモデルも用意され、実用性と走行性能を高次元で融合したモデルです。 ・トヨタ bB(2月解禁)トヨタ bBは2000年に登場した独特なボックス型デザインが特徴のコンパクトカーです。四角いフォルムと広い室内空間を持ち、カスタマイズ性の高さから若者に人気を集めました。1.3Lと1.5Lエンジンを搭載し、実用性とスタイリッシュさを両立させた革新的なモデルです。 ・ダイハツ アルティス(3月解禁)ダイハツ アルティスは、トヨタ カムリのOEMモデルとして登場した高級セダン。2.2L 直4エンジンによる滑らかな走りと快適な乗り心地、高い信頼性が特徴です。広い室内空間も魅力です。 ・トヨタ 2代目RAV4(5月解禁)2代目RAV4は、初代の成功を発展させたクロスオーバーSUVです。拡大したボディサイズと室内空間を持ちながらも取り回しの良さを維持しています。2.0L/1.8Lエンジンを搭載し、洗練されたデザインと実用性を兼ね備え、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。 ・トヨタ オーパ(5月解禁)オーパは、2000年5月に発売された5ドアハッチバックです。コンパクトなサイズながらも広々とした室内を有し、ファミリー層から人気を博しました。 ・ホンダ アコード ユーロR CL1型(6月解禁)2.2L DOHC VTECエンジンを搭載した高性能セダン。220psの最高出力と、鋭い運動性能を特徴とするスポーツモデルです。 ・ダイハツ アトレー7(7月解禁)アトレー7は、コンパクトなボディに7人乗りの3列シートを実現した実用的なミニバンです。1.3Lのエンジンを搭載し、スライドドアや折りたたみ可能な後部座席など、日常使いに便利な機能を備えています。 ・スバル インプレッサWRX STI GDB型(8月解禁)WRCで培った技術を投入した4WDスポーツセダン。2.0L水平対向ターボエンジンによる圧倒的な加速性能と、優れた操縦性を実現しました。 ・ダイハツ YRV(8月解禁)コンパクトながらも広い室内空間と個性的なデザイン、スポーティな走りを兼ね備えた実用性の高いモデルです。 ・30セルシオ(8月解禁)30セルシオは、2000年8月から製造されたトヨタのフラッグシップ高級セダン。4.3L V8エンジンを搭載し、世界トップレベルの静粛性と快適な乗り心地が特徴です。 ・9代目カローラ(8月解禁)9代目カローラは、2000年から2017年まで製造された大衆車です。空力性能を重視した流麗なデザインと、1.3L、1.5L、1.8Lのエンジンによる力強い走りを両立させています。 ・3代目シビックフェリオ(9月解禁)走行性能、実用性、どちらにもこだわってつくられたコンパクトカーです。VTECエンジンを搭載し、小さいボディながらハイパワーを誇ります。 ・トヨタ 110系 マークⅡ(10月解禁)高級感あるセダンフォルムと多彩なパワーユニットが特徴のモデルです。ツアラーVに搭載された1JZ-GTEターボエンジンによる280psの走行性能は多くのファンを魅了しています。 ・トヨタ オリジン(11月解禁)トヨタ生産台数1億台突破を記念して約1,000台のみ製造された限定車です。初代クラウンをモチーフにした豪華セダンとして注目を集めました。 ・マツダ トリビュート(11月解禁)マツダとフォードの共同開発によって生まれた、実用性と優れた走行性能を兼ね備えた小型クロスオーバーSUVです。 ・日産 エクストレイル(11月解禁)初代エクストレイルは最高280psのエンジンと「ALL MODE 4×4」で本格オフロード性能と日常の使いやすさを両立。スクエアなボディによる大容量荷室と実用的装備、優れた視界と収納で、クロスオーバーSUVの先駆けとして魅力的なモデルです。 ・トヨタ クルーガー(11月解禁)クルーガーは、2000年発売のSUVです。セダンの快適性とSUVの実用性を高次元で融合し、高い走行性能と乗り心地を実現しました。 ・スズキ グランドエスクード(12月解禁)グランドエスクードは、2.7LのV6エンジンと本格的な4WDシステムを搭載した、スズキのSUVです。高い走破性と日常の快適性を両立し、さまざまな路面状況に対応できます。 まとめ 2025年9月に25年ルール解禁を迎えるスマートシビックは、実用性と高い走行性能を兼ね備えた魅力的なモデルです。同年に解禁となる他のスポーツモデルと比べると、アメリカでの需要は限定的かもしれませんが、コンディションの良い個体は安定した価値を保つ可能性があります。 旧車王では、スマートシビックをはじめとする旧車の買取を専門に行っております。20年以上の買取実績と、累計買取件数1万5,000件を超える豊富な経験を活かし、お客様のクルマを適正価格で査定いたします。25年ルール解禁を控えたクルマの売却をご検討の際は、ぜひ旧車王にご相談ください。
