「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
旧車の売買と鑑定市場

R35 GT-Rは高リセールのプレミアムスポーツ!査定のポイントを解説
GT-R(R35)のようなスポーツカーに乗っていると、ポルシェを始めとするほかのスポーツカーにも興味をそそられてしまうものです。より走りが楽しめるクルマを求めた時に気になるのが「今乗っているGT-Rの価格はどのくらいなのか」という点ではないでしょうか。そこでこの記事では、GT-Rのリセールバリューに焦点をあて、査定を有利にするためのポイントをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。 日産GT-R(R35)とは 日産を代表するプレミアムスポーツカーです。現行のR35は2007年にモータージャーナリストとしても活躍する水野和敏氏がグローバル展開を視野に開発を手掛けたクルマでもあります。また日産社内ではGT-Rではなく、TM(トラクションマスター・トレンドメーカー)として呼ばれ、開発されてきた経緯があります。そんなGT-Rは専用開発されたプレミアム・ミッドシップパッケージを採用し、ドイツのニュルブルクリンクで磨き上げた走りが独自の世界観を作り上げ、今の絶対的な地位を確立しました。 このR35からGT-R史上初の3.8LV6型エンジンを搭載し、「匠」と呼ばれる職人が1台ずつ組み立てています。年次改良を重ねたエンジンは、最高出力419kw・最大トルク637Nmを発生し、塗装路はもちろん雪上であっても、路面をとらえて爽快に走ることができるのはGT-Rならではの特徴です。 日産GT-R(R35)のリセールバリューは良い? 結論からお伝えすると非常に良いです。具体的には、3年後のリセールバリューで76%〜85%、5年後のリセールバリューで62%〜75%、7年後のリセールバリューで71%〜76%と現行のR35は高いリセールを誇っています。ボディカラーで見ると、ブリリアントホワイトパールのリセールが良く、さらにスポーツカーの特性上、低走行車がリセールに大きく影響します。 日産GT-R(R35)で人気のグレード ここからはGT-R(R35)の人気グレードを3つご紹介します。 ピュアエディション GT-Rのベースグレードです。車種自体に十分な価値があるため、新車価格が安いながらもリセールが高く、最も人気のグレードです。足回りや機能面はほかのグレードと変わりなく、ブレンボ製のブレーキキャリパーや、20インチのレイズ製のアルミホイールを装着しており、高次元の走りを実現しています。 プレミアムエディション GT-Rの中で高級感を高めたグレードです。ピュアエディションの装備に加えて、フジツボ製のチタン合金製マフラーを採用し、洗練された外観が見る人の目を惹きつけます。さらに不快な音を消し去るアクティブノイズコントロール機能を備えたBOSEサウンドシステムや、エンジンサウンドをコントロールするアクティブサウンドコントロールを標準装備しています。走りの質とプレミアムスポーツカーとしてより満足度の高い装備を求めるユーザーに人気のグレードです。 ブラックエディション GT-Rの中でスポーツ性能を求めたグレードです。プレミアムエディションと同様にBOSEサウンドシステムを備え、シートヒーター機能を持つ、専用のレカロ製フロントシートが標準されています。シフトノブにレッドステッチが入り、本革巻きのステアリングホイールと相まって、走りの良さを予感させるインテリアが人気のグレードです。 日産GT-R(R35)の査定ポイント ここからはGT-R(R35)を査定する時にポイントとなる3つの項目をご紹介します。 走行距離 1つ目は、査定の基本となる走行距離です。目安として、1万km走行距離が伸びるごとに約50万円ほど査定価格が落ちる傾向があります。クルマの寿命ともいえる走行距離は、GT-Rにとっても重要な査定の要素です。5万kmが1つのラインになりますが、特に3万km以下の場合には、高額査定が期待できます。 サーキット走行の有無 GT-Rはサーキット走行も可能なスポーツカーですが、クルマに大きな負担がかかるサーキット走行は査定では不利になります。一般道や高速道路の走行とは比にならないダメージが残るため、どれだけキレイな状態を保っていたとしても、プロの査定士には分かります。日常使いの中で走りを楽しんでいる方が、査定では有利といえるでしょう。 点検記録簿の有無 メンテナンスの証明になる点検記録簿は、プラス査定に働く重要な項目です。ディーラーで整備してもらった後にもらう点検記録簿は意外とかさばるため、保管が面倒になって紛失してしまうケースも多いです。しかし、大切に乗っていることを客観的に示せる貴重な資料なので、査定時に提示できるようにあらかじめ1ヶ所まとめておくと良いでしょう。 まとめ この記事では、GT-Rのリセールバリューについて紹介しました。2023年には次期型が登場すると噂されており、モデルチェンジを迎えれば現在のリセールよりも下がるのは避けられません。今が最も高い査定が期待できます。

【2025年解禁】トヨタ・クレスタがついに25年ルール対象に!海外輸出で相場が高騰中
1990年代後半から2000年初頭にかけて、名車と呼ばれたトヨタのセダン「クレスタ」。その中でも2000年4月登録の一部グレードが、2025年にいよいよ25年ルール解禁の対象となります。特に北米市場では、「右ハンドルのスポーツセダン」「1JZ-GEエンジン搭載モデル」などに熱い注目が集まっており、中古車市場でも価格が高騰し始めています。 この記事は、25年以上にわたって旧車・クラシックカーを15,000台以上買い取りしてきた旧車王が、クレスタが25年ルールの対象になる背景や、具体的な解禁モデル、相場・輸出動向をわかりやすく解説します。 25年ルールとクレスタの関係性 アメリカを中心とした海外市場には、日本の中古車が人気を集める“25年ルール”という制度があります。これは、製造から25年以上経過した車輌であれば、衝突安全基準や排ガス規制を満たしていなくても「クラシックカー」として輸入が許可されるという制度です。 このルールにより、25年経過した日本車は「輸出解禁車」として注目され、特にスポーツ系・希少モデルにおいては、海外バイヤーが競って買い付けに来る傾向があります。 トヨタ・クレスタは、マークIIやチェイサーと並ぶ“3兄弟”の一角を担った高級ミドルセダン。中でも2000年4月登録の「エクシード」や「スーパールーセント」などのプレミアムエディションは、2025年4月に25年ルール解禁を迎えるモデル群です。これにより、アメリカをはじめとした右ハンドルマニアの多い地域での輸出ニーズが急増する可能性があります。 2025年に解禁となるクレスタのグレード一覧 2025年に25年ルールの対象となるクレスタは、2000年4月および12月登録のモデルです。対象車輌は、いずれも「GF-」で始まる型式を持ち、直列6気筒エンジン「1G-FE」または「1JZ-GE」を搭載しています。 特に「1JZ-GE」は、トヨタが誇る名機のひとつ。耐久性とパワーを兼ね備え、海外のチューナーたちから高い評価を得ており、輸出人気も高まる傾向にあります。 以下に、25年ルール対象となる主なクレスタのグレードと型式を一覧でご紹介します。 メーカー 車名 グレード 型式 エンジン型式 トヨタ クレスタ 2.0 エクシード プレミアムエディション GF-GX100 1G-FE トヨタ クレスタ 2.0 スーパールーセントFOUR プレミアムエディション GF-GX105 1G-FE トヨタ クレスタ 2.5 エクシード プレミアムエディション GF-JZX100 1JZ-GE トヨタ クレスタ 2.0 エクシード プレミアムエディションG GF-GX100 1G-FE トヨタ クレスタ 2.0 スーパールーセントFOUR プレミアムエディションG GF-GX105 1G-FE トヨタ クレスタ 2.5 エクシード プレミアムエディションG GF-JZX100 1JZ-GE これらの車両は2025年にアメリカへの輸出が解禁される見込みであり、国内の中古車買取業者や輸出業者からの査定額アップも期待できます。 なぜ今クレスタの価値が上がっているのか かつて街中でよく見かけたクレスタですが、近年その価値が再評価されています。とくに1990年代~2000年代初頭に生産された100系クレスタは、直6エンジン+FR(後輪駆動)という今では希少なパッケージングを持ち、国内外に愛好家がいます。 とりわけアメリカ市場では、25年ルールによって2000年式のクレスタが2025年から合法的に輸入・登録できるようになるため、海外バイヤーの注目度が急上昇。これに伴い、日本国内でも価格が高騰しはじめています。 また、クレスタに搭載されたエンジンの1G-FEや1JZ-GEは、現在のダウンサイジング・ターボ全盛の時代では味わえない、滑らかな吹け上がりと力強い加速感をもたらします。 こうした希少性・機械的魅力・海外需要の高まりが相まって、クレスタは単なる「古いセダン」ではなく、投資対象としても注目される旧車となっているのです。 クレスタを高く売るためのポイント 25年ルール解禁で注目が集まる今、クレスタを少しでも高く売却するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。単に年式や走行距離だけでなく、「誰に・どこで・どのように売るか」が価格を大きく左右します。 まず大切なのは、海外輸出に強い業者を選ぶことです。アメリカをはじめ、クレスタの輸出需要が高い国をターゲットにしている業者であれば、国内の相場よりも高値で買い取ってもらえる可能性が広がります。 次に、カスタムの有無や整備記録の有無をしっかり伝えること。純正状態が保たれているクレスタは、コレクターや海外市場での評価が高く、査定額アップにつながります。逆に社外パーツが多くても、専門業者であればその価値を正しく見極めてくれるため、事前に仕様やパーツの情報を整理しておきましょう。 また、車輌の写真を撮影しておくこともおすすめです。外装・内装・エンジンルーム・メーター周辺など、状態がわかるように複数の角度から撮影しておくことで、見積もり精度が上がり、業者とのやりとりもスムーズになります。 さらに、複数の業者に査定依頼を出すことで、最高額を引き出すチャンスが広がります。大手買取業者だけでなく、旧車専門・輸出特化の業者にも依頼して比較することが重要です。 まとめ 1999年〜2000年に製造されたトヨタ・クレスタは、2024年~2025年にかけて「25年ルール」の対象となり、北米市場を中心に輸出需要が高まりつつあります。特に1JZエンジンを搭載したスポーティモデルや、プレミアムエディションなどの特別仕様車は、国内外のファンから注目されており、相場も上昇傾向にあります。 売却を検討している方は、国内の中古車相場だけで判断せず、「輸出需要」「希少性」「状態の良さ」などを武器に、海外バイヤーのニーズにも対応できる買取業者を選ぶことが大切です。複数の業者を比較し、写真や仕様情報をしっかり伝えることで、思わぬ高額査定が出る可能性もあります。 クレスタはただの旧車ではなく、「投資価値」や「コレクション価値」を持つ資産ともいえる存在です。手放す前に一度、価値を正しく見極めてくれる専門業者に相談してみてはいかがでしょうか。

カイエンのリセールバリューは?買取相場や高く売る方法も紹介
ポルシェの人気車種であるカイエンは高いリセールバリューが期待できると聞き、自身のクルマがどの程度で売却できるのか気になっている方もいるでしょう。 カイエンは、ほかの輸入車に比べてリセールバリューが高い傾向があります。 この記事では、カイエンの買取相場やリセールバリューのポイント、少しでも高く売る方法について紹介します。 ポルシェ カイエンとは 2002年に登場したポルシェ初のSUV「カイエン」は、スポーツ性能が低いとされがちなSUVに、ポルシェ独自のスポーティさを融合させたモデルです。従来のSUVのイメージを覆し、2022年には販売台数の約3分の1を占める大ヒットモデルとなりました。 初代モデルの955型には、下記のグレードが設定されており、いずれも高出力なエンジンを搭載しています。 ・カイエンS:V型8気筒エンジン(4,510cc、250KW)・カイエン・ターボ:V型8気筒ツインターボエンジン(4,510cc、331KW)・カイエン(ベーシックモデル):狭角V型6気筒エンジン(3,189cc、184KW) 高出力なエンジンにより、SUVでありながらスポーツカーのようなダイナミックな走行を実現しました。中でも、カイエン・ターボは「911」や「ボクスター」などのスポーツカーに匹敵する性能を持っており、発進からわずか5.6秒で100km/hに達します。 また、ポルシェの伝統的なDNAを受け継ぎつつ、SUVならではの居住性と実用性も兼ね備えています。日常での使い勝手のよさとファミリーカーとしての快適さを両立しているため、アウトドアや長距離ドライブでも頼もしいパートナーとなるでしょう。 なお、955型のほかに下記のモデルが販売されており、2代目以降はハイブリッドモデルもラインナップとして加わっています。 ・2006年:957型(マイナーチェンジ後)・2010年:958型(2代目)・2018年:E3K30型(3代目) カイエンはブランドの持つ高級感と、SUVの実用性を兼ね備えたモデルとして、今後もポルシェを牽引していくでしょう。 ポルシェ カイエンの買取相場 初代モデルのカイエンの買取相場は、下記のとおりです (2024年9月時点)。 型式・グレード 買取相場価格 955型 ターボ 30万~200万円 957型 50万~200万円 957型 ターボ 50万~350万円 現行モデルと比べると買取相場に差があるものの、初代モデルでも高ければ350万円程度で売却できます。グレードや装備品によって買取価格が変動するため、正確な金額を把握したい場合は査定を依頼しましょう。 ポルシェ カイエンのリセールバリューが高い理由 カイエンは、優れた走行性能や高いブランド力、根強いファンの存在により、高いリセールバリューを維持しています。ここでは、カイエンのリセールバリューが高い理由を紹介します。 優れた走行性能 カイエンは、ポルシェが手がけた初めてのSUVながら、スポーツカーに劣らない走行性能を持つモデルです。一般的なSUVとは一線を画す高い走行性能により、ポルシェらしいダイナミックでスポーティーな走りを実現できるため、多くのファンに支持されています。 また、ガソリンエンジンに加えて、ターボエンジンやハイブリッドエンジンも展開しており、幅広いニーズに応えられることもリセールバリューに影響しているでしょう。 高いブランド力 カイエンのリセールバリューが高値で推移しやすい要因の1つに、ポルシェの高いブランド力があります。 一般的に輸入車は国産車よりリセールバリューが低い傾向にあるものの、圧倒的なブランド力を誇っているポルシェは、他のメーカーと比べて価格が大きく落ちることがありません。また、単にブランドイメージがよいだけではなく、品質やパフォーマンスに対する信頼も厚いことも、リセールバリューを押し上げる要因となっています。 根強いファンの存在 根強いファンの存在も、カイエンのリセールバリューを支える要因の1つです。登場初期は、伝統的なポルシェを求めるファンからの評価は低かったものの、現在では初代カイエンを含め、年式を問わず高い人気を誇ります。 特にクラシックポルシェは、多くのファンから支持されており、発売から20年以上経過している955型(初代モデル)は現在でも高い人気を誇っています。 ポルシェ カイエンを高く売る方法 定期的なメンテナンスで良好な状態を維持し、走行距離をなるべく抑えれば、カイエンを高く売れる可能性があります。続いて、カイエンを高く売る方法を紹介します。 定期的なメンテナンスで状態を維持する カイエンを高く売るには、定期的なメンテナンスで良好な状態を維持しましょう。しっかりとメンテナンスされているクルマは、大切に扱われている印象を与えられるため、査定員からの評価が高まる可能性があります。 具体的には、下記の基本的なメンテナンスを欠かさず行ってクルマの性能を維持し、将来的なトラブルを防ぎましょう。 ・オイル交換・ブレーキの点検・タイヤの点検や交換・エアフィルターの交換 など なお、査定前に車内外をきれいにしておくこともプラス評価につながります。 走行距離をなるべく抑える カイエンを高く売るには、走行距離をなるべく抑える必要があります。なぜなら、走行距離が少ないクルマほど状態がよいと判断されるためです。 特に、下記の部品は走行距離が増えると劣化が進みやすいといわれています。 ・エンジン・トランスミッション・サスペンション いずれも走行に関わる重要な部品です。カイエンの売却を決めたら、直前の長距離運転を避けて、走行距離を抑えましょう。 ポルシェ カイエンの売却は旧車王へご相談ください カイエンは名実ともにポルシェを代表する車種の1つです。売却する際には、その価値を熟知している買取業者に依頼するとよいでしょう。 カイエンの売却をご検討の際は、ぜひ旧車王へお問い合わせください。旧車王は、旧車に特化して20年以上買取を実施しており、ポルシェの車種を数多く取り扱っております。 他の買取業者では見逃してしまう部分も徹底的に鑑定するため、売却先にお悩みの場合は、ぜひ旧車王にご相談ください。

廃車費用の相場と内訳を完全ガイド!無料で処分して損しないための知識
長年連れ添った愛車を手放すとき、手続きや必要な費用が心配になる方は多いのではないでしょうか。 廃車にかかる費用は依頼先によって大きく異なり、工夫次第では費用をかけずに処分することも可能です。場合によっては、思わぬ金額が手元に戻ってくるケースもあります。 この記事は、25年以上にわたって旧車・クラシックカーを15,000台以上買い取りしてきた旧車王が、廃車にかかる費用の内訳や詳しい相場、損をしないための依頼先の選び方について解説します。 廃車手続きの種類 廃車の手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」があります。どちらの手続きを選ぶかによって、その後のクルマの扱いや必要となる費用が変わります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 永久抹消登録 永久抹消登録は、クルマを解体(スクラップ)することを前提とした手続きです。対象のクルマの登録情報を永久に抹消します。この手続きが完了すると、そのクルマは二度と公道を走ることができなくなります。 災害等でクルマが使えなくなった場合や、老朽化等により乗る予定が全くないクルマを処分する際に選ぶことが一般的です。手続きを行うと、後述する自動車税や重量税の還付金を受け取ることができます。クルマを完全に手放し、維持費の負担から解放されたい場合に適した方法です。 一時抹消登録 一時抹消登録とは、クルマの登録を一時的に中断する手続きを指します。海外出張や長期入院などで長期間クルマに乗らないものの、将来的にまた乗る可能性がある場合に利用されます。手続きを行うと、ナンバープレートを返却するため公道を走行できなくなりますが、クルマ自体は手元に残しておくことが可能です。 登録を抹消している期間は、自動車税の支払いが不要です。再びクルマに乗る際には「中古車新規登録」の手続きを行えば、再び公道を走れるようになります。ただし、クルマを保管しておく駐車場は必要であるため、維持費が完全に発生しなくなるわけではありません。 廃車にかかる費用の相場 廃車の手続きには、具体的にどのような費用が発生するのでしょうか。ここでは、廃車手続きで発生する可能性のある代表的な費用の内訳と、それぞれの相場を紹介します。 解体費用 解体費用は、永久抹消登録の際に発生するクルマをスクラップにするための作業費用です。解体業者がクルマのエンジンや各種パーツを取り外し、プレス機で圧縮して鉄の塊にするまでの一連の工程が含まれます。 費用は業者によって幅がありますが、一般的には2万円程度と考えておくとよいでしょう。業者によっては、解体して得られる鉄資源を売却することで利益を得るため、解体費用を無料にしているところもあります。依頼する前に、解体費用がいくらかかるのかを必ず確認しましょう。 レッカー料金 レッカー料金は、事故や故障などで自走できなくなったクルマを、解体工場まで運搬する費用です。移動距離に比例して高額になるのが一般的であり、数キロ程度の近距離であれば5,000円程度、長距離になると3万円以上かかることがあります。 クルマが問題なく走行できる状態であれば、オーナーが自身で解体工場まで持ち込むことで、レッカー料金を節約できます。廃車費用を少しでも抑えたい場合、クルマが自走可能かどうかは大きなポイントになります。 リサイクル料金 リサイクル料金は、クルマを解体した後に残るシュレッダーダスト(細かく破砕されたゴミ)やエアバッグ類などを、環境に配慮して適正に処理するために必要な費用です。 2005年に施行された自動車リサイクル法に基づき、原則としてクルマの購入時に前払いする義務があるため、多くの場合は廃車時に改めて支払う必要はありません。 購入時に支払い済みであることは「リサイクル券」が証明します。リサイクル券を紛失したとしても、支払いの記録はシステムで管理されているため再度支払う必要はありません。ただし、法律が施行される2005年より前に購入し、一度も車検を受けていないようなケースでは、リサイクル料金が未払いの可能性があります。 その際にはリサイクル料金を支払う必要があり、車種によって1万円から2万円程度が請求されます。 手続きにかかる申請手数料 廃車手続きを運輸支局で行う際には、申請手数料が発生します。永久抹消登録や一時抹消登録の手続き自体は無料ですが、登録事項等証明書の交付を受ける場合などに、数百円程度の手数料が必要になることがあります。また、業者に手続きを代行してもらう場合は、これらの手数料に加えて「代行手数料」が上乗せされるのが一般的です。 【依頼先別】廃車費用の相場 廃車にかかる費用は依頼先によって金額が変わります。ここでは、代表的な3つの依頼先である「ディーラー」「自分で手続き」「廃車買取業者」それぞれのメリット・デメリットを、費用の観点から比較します。 ディーラーに廃車依頼する ディーラーに廃車を依頼する場合、新しいクルマの購入と同時に手続きを進めるのが一般的です。新車購入時の下取りと合わせて廃車手続きを任せられるため、手間がかからず安心感を得られるのがメリットといえます。 ただし、費用面では割高になる傾向があります。ディーラーによる廃車手続きは外部の解体業者へ委託するケースが多いため、解体費用やレッカー代に代行手数料が上乗せされることがほとんどです。そのため、廃車にかかる費用の総額は、1万円から8万円程度が相場です。手間をかけたくない方や、新車購入を前提としている場合には良い選択肢となりますが、費用を抑えたい方にはあまり向いていない方法です。 自分で廃車手続きをする 自分で運輸支局に出向いて手続きを行えば、ディーラーや業者に支払う代行手数料を節約できます。必要な書類を自分で揃え、平日に運輸支局へ行く時間を確保できるのであれば、最も安く済ませられる可能性のある方法です。 ただし、かなりの手間と時間、さらには専門知識を要します。クルマを解体してくれる業者を自分で探し、レッカーの手配も行わなければなりません。その後は書類作成や運輸支局での手続きなど、すべてを自分1人で行う必要があります。手間を惜しまず、少しでも費用を節約したい方に向いている方法です。 廃車買取業者に依頼する 廃車費用を抑えたい場合は、廃車買取業者に依頼することも方法の1つです。廃車専門のプロフェッショナルであり、手続きにかかる費用を無料にしているところが少なくありません。 無料で引き取れる理由は、買い取ったクルマをただスクラップにするのではなく、価値のある部品やパーツを再利用したり、鉄資源として売却する独自のノウハウを持っていたりするためです。 特に海外では日本車の人気が高いため、日本では価値がないとされる古いクルマや過走行車でも、修理したうえで輸出すれば利益を得られます。そのため、手続きの代行費用やレッカー代、解体費用まで、すべて無料で対応できます。 クルマの状態や車種によっては値段がつき、買い取ってもらえる可能性もあります。 廃車にすると還付金を受け取れる 廃車にすると、条件を満たした場合に国や保険会社から「還付金」を受け取れます。これは、クルマの所有者が前払いしている税金や保険料の一部が返還される仕組みです。還付金の詳細について見ていきましょう。 自動車税の還付 自動車税は、廃車手続きを行うことで還付されます。自動車税は、毎年4月1日時点の所有者が、その年度分(4月から翌年3月まで)をまとめて前払いしています。そのため、年度の途中で永久抹消登録または一時抹消登録を行うと、残りの月数に応じた税金が月割りで還付されます。 たとえば、9月に廃車手続きが完了した場合の還付金は、10月から翌年3月までの6ヶ月分です。ただし、還付制度は普通自動車・小型自動車が対象であり、軽自動車税は還付されません。 重量税の還付 自動車重量税の還付は、永久抹消登録を行った場合にのみ受けられます。自動車重量税は、車検時に次の車検までの期間分(通常は2年)を支払う税金です。車検の有効期間が1ヶ月以上残っている状態でクルマを適正に解体し、永久抹消登録と還付申請を同時に行うことで、残存期間に応じた金額が還付されます。 自動車重量税の還付を受けるためには、解体報告の記録と永久抹消登録が完了していることが条件となるため、手続きを忘れないようにしましょう。なお、クルマの存在が残る一時抹消登録は還付の対象にはなりません。 自賠責保険料の返戻金 自賠責保険料の返戻金は、税金の還付とは異なり、ご自身が加入している保険会社に直接解約手続きを行なうことで受け取れます。保険の契約期間が1ヶ月以上残っている場合に、残りの期間に応じた保険料が月割りで返還される仕組みです。 永久抹消登録または一時抹消登録手続きの完了後、証明となる書類を保険会社に提出して解約を申請します。手続きを行うことで、数千円から1万円程度の返戻金を受け取れる可能性があるため、忘れずに申請しましょう。 廃車費用を抑えるためのポイント 廃車費用は依頼先やクルマの状態によって大きく変動します。ここでは、誰でも実践できる費用節約のための具体的なポイントを3つ紹介します。 自走できればレッカー代を節約できる 廃車費用の中で大きな割合を占めるのがレッカー代です。もしクルマが安全に走行できる状態であるなら、オーナーが自身で運転して業者に持ち込むことで、レッカー代の支払が不要になります。 車検が切れていても、仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を市区町村の役所で取得すれば、合法的に公道を走行させることが可能です。 近場の解体業者を選ぶ クルマが自走できずにレッカー移動が必要な場合は、なるべく自宅から近い場所にある業者を選ぶことをおすすめします。レッカー料金は移動距離によって決まるため、業者までの距離が短ければ短いほど、費用を安く抑えることが可能です。 複数の業者に見積もりを依頼する際には、レッカー代の金額に加えて、料金が無料になる条件を事前に確認しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。地域に密着した業者を探してみるのも1つの方法です。 価値がわかる業者に買取を依頼する 廃車費用を抑えるだけでなく、利益を得られる可能性がある方法が、クルマの価値を評価してくれる業者に依頼することです。特に廃車買取を専門に扱っている業者は、古いクルマや走行距離が多いクルマでも、価値を見出すノウハウを持っています。 動かなくなったクルマでも、希少な純正パーツには高い価値があるかもしれません。また、一部の車種は海外で絶大な人気があるため、廃車同然のクルマが高値で取引されることもあります。 一般的な中古車販売店では0円と査定されるようなクルマでも、専門業者に依頼すれば思わぬ価格で買い取ってもらえるかもしれません。 まとめ 廃車にかかる費用は、クルマの状態や手続きの種類、そして依頼先によって大きく変わります。廃車買取専門業者に依頼すれば、面倒な手続きを無料で代行してくれるだけでなく、動かなくなったクルマや古いクルマでも価値を見出し、買い取ってくれる可能性があります。 「廃車だから費用がかかるのは仕方ない」と諦めてしまう前に、まずは専門の業者に相談してみましょう。

エンジンがかからない車でも買取できる?故障車の売却方法とは
エンジンがかからなくなったクルマの処分を検討する際、売却を検討する方は多いのではないでしょうか。エンジンがかからない状態のクルマの多くは買取の対象となります。廃車手続きの費用やレッカー代を支払う必要なく、思わぬ金額で売却できるケースも珍しくありません。 この記事は、25年以上にわたって旧車・クラシックカーを15,000台以上買い取りしてきた旧車王が、エンジンがかからないクルマが買取の対象となる理由や具体的な売却方法、少しでも高く売却するためのポイントについて解説します。 エンジンがかからない車は「不動車」 エンジンがかからない、あるいはかかっても自走できない状態のクルマは、一般的に「不動車」と呼ばれます。クルマが動かなくなる原因はさまざまで、一概に「故障」と断定できるものばかりではありません。 たとえば、長期間クルマを動かさなかったことによるバッテリー上がりは、不動車の代表的な原因の1つです。また、燃料タンクが空になっている、あるいはガソリンが劣化しているといった「ガス欠」や燃料系のトラブルや、エンジン本体やトランスミッション、タイミングベルト、スターター(セルモーター)といった機関系の故障が原因になるケースもあります。 「エンジンがかからない」と一言でいっても原因は多岐にわたるうえに、原因の重大性や修理にかかる費用によって、クルマの価値や買取の可否も大きく変わります。 エンジンがかからない車の維持費 エンジンがかからないクルマを所有し続けるうえで、見過ごせないのが維持費の問題です。公道を走らずにガレージや駐車場に置いているだけだとしても、税金や保険料といったコストは発生し続けます。 大きな負担となるのが、毎年4月1日時点の所有者に課せられる「自動車税(種別割)」です。排気量に応じて課税されるこの税金は、クルマを使っていなくても納付義務が生じます。 さらに、これらに加えて、月々の駐車場代もかかります。 クルマの利用状況を問わずに発生するこれらの維持費は、クルマを放置する期間が長引けば長引くほど、負担が増えていきます。エンジンがかからないクルマを放置しておくことは、経済的な観点から見ても決して得策とはいえません。いずれ売却や処分を考えているのであれば、無駄な維持費がかさむ前に、早めに行動を起こすことが賢明な判断といえるでしょう。 エンジン故障車を買い取ってくれる業者 エンジンがかからない不動車を売却しようと考えたとき、どこに相談すればよいのでしょうか。クルマの買取を行っている業者にはいくつかの種類があり、それぞれに得意分野や特徴があります。エンジン故障車を買い取ってくれる業者の種類とそれぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。 中古車販売店 中古車販売店は、買い取ったクルマを再販することを主な目的としています。そのため、エンジンがかからないクルマの買取には積極的ではない傾向があります。 修理が比較的簡単かつ人気車種であれば、買取に応じてもらえる可能性はありますが、買取価格は市場での販売価格から修理費用等を考慮した金額となるため、高値は期待できません。 ディーラー 新車の購入時に、現在乗っているクルマを引き取ってもらう下取りという形で、ディーラーに売却する方法もあります。 ディーラーの主な目的は新車の販売であり、下取りはそのためのサービスの1つです。再販が難しい不動車に対してはほとんど価値がつかないことが多く、査定額が0円となることも珍しくありません。クルマの状態によっては、レッカー代や廃車手続きのための費用を請求されてしまう可能性すらあります。 廃車買取業者 廃車買取業者は、エンジンがかからないクルマや事故車、水没車といった、一般的な市場では価値がつかないとされるクルマの買取を専門としています。これらの業者はクルマを「中古車」として捉えず、「資源」や「部品」として扱います。 そのためクルマがどのような状態であっても、最低限の金属資源としての価値を保証してくれることが多く、買取価格が0円になることはほぼありません。廃車手続きの代行費用やレッカー代を無料にする業者が多いのも大きな魅力です。確実に値段をつけて引き取ってほしい場合には、もっとも頼りになる選択肢の1つです。 買取専門店 買取専門店は、中古車販売店やディーラーとは異なり、買取を専門に行っています。最大の特徴は、独自の多様な販売ルートを持っている点です。国内での再販はもちろん、海外への輸出、部品としての販売、オークションへの出品など、買い取ったクルマを最も高く売れるルートを確保しています。 これらの販路の中には、エンジンがかからないクルマに価値を見出すものが含まれていることがあります。日本では人気がなくても海外では絶大な需要がある車種や、特定の部品に価値がある希少なクルマは、不動車であっても驚くような高額査定が提示される可能性があるでしょう。 エンジンがかからない車でも買取される理由 クルマは数万点もの部品から構成される精密機械であり、動かなくなったとしても、その価値が完全に失われるわけではありません。専門業者が不動車を買い取るのには、明確な理由があります。エンジンがかからない車でも買取される理由について詳しく見ていきましょう。 部品や資源としての価値がある クルマには、再利用可能な価値ある部品が数多く搭載されています。エンジンの故障で不動車になったとしても、トランスミッションや足回りのパーツ、バンパーやドアといった外装部品、シートやカーナビなどの内装品は十分に使える状態かもしれません。これらの部品はリサイクルパーツとして取り外され、修理用の部品として販売されます。 特に、すでに生産が終了している旧車の純正部品は希少価値が高く、高値で取引されることもあります。全ての部品を取り外した後の車体も、鉄やアルミニウムなどの金属資源として価値を見出されることが少なくありません。 海外需要がある 日本車は、その品質の高さと耐久性から、世界中で非常に高い評価を受けています。日本では「古い」「走行距離が多い」といった理由で価値が低いと見なされるクルマでも、海外の国々、特に新興国では「まだまだ現役で走れる信頼性の高いクルマ」として、大きな需要があります。 エンジンがかからない状態であっても、現地の整備工場で安価に修理して再販できるため、買取業者は積極的に買い付けを行います。買取業者は独自の輸出ルートを持っており、どの国でどの車種が人気なのかを熟知しています。そのため、国内では価値がないと思われているような不動車でも、海外の需要を見越して想像以上の価格で買取してくれることがあります。 エンジン故障車の買取相場 エンジンがかからないクルマの買取価格は、車種や年式、走行距離、そしてクルマの状態によって大きく変動するため、相場を断定することは困難です。しかし、査定額を左右する要件と目安を知っておくことで、事前にある程度の対策ができるようになります。エンジン故障車の買取相場について詳しく見ていきましょう。 状態が良い場合の相場 不動車であっても、内装の状態が良く年式が新しいクルマは、ある程度高額の査定が期待できます。また、バッテリー交換や簡単な部品交換で直る程度の不動車であれば、修理費用が数万円程度に収まるため、こちらも比較的高い買取価格がつきやすいでしょう。 一方で、エンジン本体の載せ替えが必要になるような重度の故障は多額の修理費用がかかるため、買取価格は低くなる傾向にあります。 走行距離が長い場合の相場 走行距離が10万kmを超えているような過走行車のエンジンがかからない場合、国内での再販は難しいため、買取価格は低くなるのが一般的です。多くの買取店では、部品取り用あるいは海外への輸出を前提とした価格設定になるでしょう。 ただし、これも車種によります。例えば、耐久性に定評のあるランドクルーザーやハイエースといった車種は海外での需要が非常に高いため、エンジンがかからない過走行車であっても値段がつくでしょう。所有しているクルマが海外で人気のあるモデルかどうかで、買取相場は大きく変わります。 全く動かない車の相場 損傷や劣化が大きく、修理して再び走らせることが現実的ではないクルマの査定額は、主に部品や金属資源に基づいた金額となります。 この場合、廃車買取業者が主な買取先となり、数万円程度の買取になることが多いです。 ただし、希少なクラシックカーや限定モデルであれば話は変わります。コレクターや専門業者にとっては、レストア(復元)のベース車両や純正部品の供給源となるため、高い査定額がつくことがあります。 エンジンがかからない車を高く売るためのポイント 売却を諦めていたクルマに値段がつく可能性があると分かったら、次は「どうすれば少しでも高く売れるのか」を考えたいところです。エンジンがかからないクルマでも、次のポイントを押さえることで、査定額がアップする可能性があります。 車をきれいにして査定に出す 査定額を上げるためには、査定士にクルマを大切に扱ってきたという印象を与えることが重要です。ホコリまみれのクルマよりも、きれいに手入れされたクルマの方が、査定士の心証は格段に良くなります。 丁寧に扱われているクルマは、エンジン以外のパーツの状態も良好な可能性が高いため、プラス評価につながります。 複数業者に査定を依頼する 高価買取を実現するために効果的な方法の1つが、複数の買取業者に査定を依頼する相見積もりです。1社だけの査定では、適正な査定額を判断するのは困難です。 複数の業者に査定を依頼することで、業者間に競争が生まれます。他社の査定額を交渉材料に使い、より高い金額を引き出せる可能性があります。 特に、不動車の査定額は業者によって評価基準が大きく異なるため、廃車買取業者や買取専門店など、タイプが異なる複数の業者に見積もりを依頼した方がよいでしょう。 相場を把握して交渉に備える インターネットの一括査定サイトなどを利用し、自分のクルマがどのくらいの価格で取引されているのか、おおよその相場を把握してから査定に臨むことも大切です。もちろん、エンジンがかからない場合は、相場よりも大きく下がります。 しかし、ある程度の目安にはなるため、不動車であることを考慮しても相場よりも著しく安い査定額ではないかどうかを判断しやすくなります。 オプションをしっかり伝える クルマに取り付けられているオプションパーツも、査定額に大きく影響します。メーカー純正のナビゲーションシステムやサンルーフ、本革シートといった人気の高いオプションは、大きなプラス査定の対象になる傾向があります。 有名ブランドのアルミホイールやマフラー、エアロパーツといった社外品のパーツも、クルマ好きには評価されるポイントです。査定の際には、オプションやカスタムパーツの存在を忘れずに査定士にアピールしましょう。取り外して保管している純正パーツがあれば、それも一緒に提示するとさらに評価が上がることがあります。 まとめ エンジンがかからないというだけで、クルマの価値をゼロだと決めつけてしまうのは早計です。たとえ自走できなくても、部品や資源としての価値、あるいは海外での需要といった価値が眠っている可能性があります。 不動車は売却先によって、買取価格が大きく異なります。動かなくなったクルマの処分を検討する際には専門性の異なる複数の買取業者から見積もりを取得し、クルマの価値を高く適切に評価してくれる業者を選びましょう。

車の出張買取とは?利用する流れや注意点も解説
クルマの売却を考えているものの、買取店まで出向くことが難しい場合は「出張買取」を利用する方法があります。 出張買取は、指定した時間と場所に鑑定士(査定士)が訪問してクルマを査定するサービスです。仕事や育児などで忙しい方や車検切れで走行できないクルマを売却したい人は、出張買取を活用するとよいでしょう。 この記事は、25年以上にわたって旧車・クラシックカーを15,000台以上買い取りしてきた旧車王が、出張買取の仕組みや持ち込み査定との違い、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。 車の出張買取とは 出張買取とは、自宅や勤務先などの指定した場所に買取業者の鑑定士(査定士)が訪問し、クルマを査定してもらえるサービスのことです。 買取業者の店舗にクルマを持ち込まずに査定を受けられるだけでなく、提示された査定額に納得した場合はその場で契約を結ぶことも可能です。 見込み顧客を獲得する営業活動の一環として行われるサービスのため、多くの買取業者は出張料や査定料などを無料としています。査定額が希望と合わなければ、気兼ねなく断ることができます。 持ち込み査定との違い 出張買取と持ち込み査定の主な違いは「査定をする場所」です。査定額にはほとんど差がありません。 持ち込み査定の場合、業者の店舗で査定が行われるため、クルマを運ぶ必要があります。また、査定が終わるまで店舗で待たなければならず、予約なしで訪問したときは待ち時間が長くなることもあります。 一方の出張買取は、自身が指定した場所で査定が行われるため、店舗までクルマを運転する必要がありません。持ち込み査定よりも手間や時間はかかりませんが、査定してもらうための場所は自身で確保するのが一般的です。 出張買取が向いている人 クルマの出張買取は、自身が指定する場所で査定を受けて買い取ってもらえるため、以下のような方に向いています。 ・仕事や育児などで店舗へ行く時間を確保することが難しい人 ・車検切れや故障などでクルマを動かせない人 ・自宅の近くに買取業者の店舗がない人 ・運転免許を返納した高齢者や運転に自信がない人 車の出張買取のメリット クルマの出張買取には、以下の3つのメリットがあります。 店舗に行く手間が省ける 出張買取は、買取業者が自宅や勤務先などの指定した場所まで来てくれるため、クルマを店舗へ運ぶ手間や時間が一切かかりません。 買取店の営業時間を気にしたり店舗まで運転したりする必要がなく、都合のよい場所でクルマの査定や契約、引き渡しが完結できます。 「朝早くから夜遅くまで仕事が忙しい」「小さな子どもがいて外出が難しい」など時間的な制約がある方は、出張買取の利用がおすすめです。 複数業者の査定比較がしやすい クルマを少しでも高く売るためには、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」をして結果を比較することが大切です。 複数の店舗にクルマを持ち込んで査定をしてもらう場合は手間と時間がかかりますが、出張買取であれば手軽に相見積もりができます。 同じ日時に複数の業者を呼んでクルマの査定を依頼すると、業者間の競争意識が働きやすくなり、より高い査定額を提示してもらいやすくなります。 車検切れや不動車にも対応できる 車検切れのクルマや事故・故障で動かなくなった不動車がよりスムーズに売却できる点も出張買取の強みです。 通常、車検切れのクルマはそのままでは公道を走行できないため、店舗へ持ち込むには仮ナンバーの取得が必要です。自走ができない不動車の場合はレッカー移動が必要になり、高額な費用が発生することもあります。 出張買取であれば買取業者にクルマを引き取ってもらえるため、仮ナンバーの取得やレッカー移動が不要であり、それらの費用もかけることなく売却ができます。 車の出張買取のデメリット 出張買取は便利なサービスですが、以下のようなデメリットもあります。 事前予約が必要 出張買取は、事前に買取業者とスケジュールを調整し、予約を取る必要があります。持ち込み査定のように、思い立ったその日にクルマを査定してもらうことは困難です。 また、複数の業者に相見積もりをしてもらう場合は、各社と訪問日や時間を調整する必要があり、手間がかかります。 出張買取を利用する場合は、スケジュールに余裕を持って申し込みましょう。 成約を断りづらい場合がある 出張買取は、申し込んだ人が指定する場所まで鑑定士(査定士)が時間やガソリン代、電車代などの交通費をかけて訪問してくれます。 そのため、査定額が希望に満たなかったとしても「わざわざ来てもらったのに断るのは申し訳ない」と感じて断りづらくなる場合があります。 しかし、出張査定は買取業者の営業活動の一環であるため、断っても問題ありません。他社の査定額と比較して検討したいときやクルマを売却すべきか悩んでいるときは、その旨をはっきりと伝えましょう。 トラブルや減額リスクに注意 出張買取では、契約後に査定額を下げられる「二重査定」により、買取業者とトラブルが起こることがあります。 二重査定とは、クルマを売却する契約を結んだ後に「査定時には見つからなかった不具合があった」などと理由をつけて一方的に買取価格を引き下げる手口のことです。 二重査定によるトラブルを防ぐためには、クルマのキズや不具合、修復歴などを正直に申告することが大切です。また、契約書に「車輌の引き渡し後に減額請求は行わない」といった趣旨の記載があることをよく確認し、二重査定を行わない業者を選びましょう。 出張買取の流れと利用方法 クルマの出張買取を利用する流れは以下のとおりです。 1.査定を申し込む 2.訪問日程を調整する 3.必要書類を準備する 4.クルマを査定してもらう 5.契約を結ぶ 6.車輌・書類を引き渡す 7.買取金額の入金を確認する 各手順について1つずつ解説します。 1.査定を申し込む 買取業者の公式サイトや一括査定サイト、電話などで出張査定を申し込みます。 インターネットで申し込む場合、車種や年式、走行距離といった車輌の情報、氏名や住所、連絡先などの個人情報を入力することになるため、自動車検査証(車検証)を手元に用意しておくとスムーズです。 2.訪問日程を調整する 査定の申し込みが完了すると、買取業者の担当者から電話やメールで連絡が入ります。その際に、鑑定士(査定士)に訪問してもらう日時や場所を調整します。 買取業者によっては、このタイミングでおおよその買取価格を教えてもらうことも可能です。 3.必要書類を準備する 出張買取の日程が決まったら、クルマの売却時に必要となる書類を準備しておきましょう。 自動車検査証のみでも査定を受けることはできますが、必要書類を準備していれば、査定当日に契約とクルマの引き渡しまで済ませることも可能です。 必要書類は、普通自動車と軽自動車で異なります。 書類名 普通自動車 軽自動車 自動車検査証(車検証) 〇 〇 自動車税納税証明書 〇 〇 自賠責保険証 〇 〇 リサイクル券 〇 〇 印鑑登録証明書 〇 △※1 実印 〇 △※1 認め印 × 〇 譲渡証明書※3 〇 × 委任状※3 〇 × 住民票 △※2 △※2 ※1:原則として不要だが、買取業者によっては本人確認のために提出を求められる場合がある ※2:車検証に記載されている住所や姓、所有者などが売り手の実情とは異なる場合に必要 ※3:譲渡証明書及び委任状は買取業者が用意してくれるケースがほとんど 必要書類は買取業者によって異なる場合があるため、日程調整の際に準備すべきものをよく確認しておきましょう。 4.クルマを査定してもらう 査定当日になると、事前に決めた日時と場所に買取業者の鑑定士(査定士)が訪問してクルマの状態を確認し、買取金額を算出します。 30分〜1時間程度が目安ですが、査定額の説明や契約に関する相談なども合わせると1時間程度はみておきましょう。 また、査定中は原則として所有者の立ち会いが必要です。鑑定士(査定士)からクルマの状態について質問されたときは、正直に答えましょう。 5.売買契約を結ぶ クルマの査定が終わり、提示された金額と売却条件に納得できたら売買契約を結びます。 契約を結ぶ際は、契約書の隅々にまで目を通し、記載内容をよく理解することが大切です。 特によく確認したい内容は以下のとおりです。 ・売買契約書にある合計金額は査定額と一致しているか ・自動車税、自賠責保険料、リサイクル料金などの未経過分の返金方法や返金の有無 ・買取金額の支払時期と支払方法 ・車種や年式、グレードなどの車輌情報は正しく記載されているか ・クルマの引き渡し後に買取金額が減額されることがあるか 不明点や疑問点があれば必ずその場で質問し、解消したうえで契約を結びましょう。 6.車輌・書類を引き渡す 売買契約を締結したら、車輌本体と必要書類を業者に引き渡します。引き渡し日は、契約時に業者と相談して決めます。 クルマを引き渡すときは、座席の下やグローブボックス、トランクなどに私物が残されたままになっていないかよく確認しましょう。 また、個人情報の漏洩を防ぐために、カーナビのデータはすべて削除するか初期化し、SDカードやUSBメモリーなどの記憶媒体は取り外すことをおすすめします。 7.買取金額の入金を確認する 車輌本体と書類の引き渡しが完了した後、通常は3営業日から1週間程度で指定した銀行口座に買取金額が振り込まれます。 契約書に記載された期日までに買取金額が適切に振り込まれていることが確認できたら、取引完了です。 出張買取を利用するときの注意点 出張買取の際、鑑定士(査定士)はクルマの外装や内装、エンジンルームなどを隅々まで確認するため、一定のスペースを確保する必要があります。 狭いガレージや機械式立体駐車場などにクルマを駐車している場合は、事前に買取業者と相談し、近隣のコインパーキングなどを借りる必要があるか確認しましょう。 また、買取業者によっては出張料や搬出料などがかかることもあるため、出張買取を申し込む際に料金体系をよく確認することもおすすめします。 出張買取で高額査定を狙うコツ 出張買取で高額査定を狙うためのポイントは以下のとおりです。 ・点検整備記録簿を準備する ・純正パーツを揃えておく ・売却予定のクルマと同じ車種の買取が得意な業者を選ぶ 査定の際に、点検や整備の履歴がわかる「点検整備記録簿」を提示すると、クルマが定期的にメンテナンスされてきたことを証明でき、より査定額が高くなる可能性があります。 車種や年式、グレードなどが同じであっても、買取業者によって査定結果が異なることがあります。出張買取を依頼するときは、売却を予定しているクルマと同じモデルを専門的に買い取る業者を選ぶとよいでしょう。 まとめ 出張買取を利用すると、店舗に行く手間を省くことができ、複数の業者の査定結果も比較しやすいため、より手軽に高値でクルマを売却することが可能です。 一方で、事前に予約が必要であり、当日に訪問してもらうことは難しい場合があります。また、契約後に買取価格を不当に引き下げる「二重査定」によるトラブルが発生するケースもあるため、安心して任せられる業者を選ぶことが重要です。

ハコスカ(3代目スカイライン/C10型)のリセールバリューは高い!人気の理由や高く売るコツを解説
ハコスカの愛称で親しまれている日産 3代目スカイライン(C10型)は、旧車の中でも高い人気を誇るモデルです。今回は、ハコスカの人気が高い理由やリセールバリューについて紹介します。ハコスカを売却するときの参考にしてみてください。 ハコスカは圧倒的な人気を誇る旧車 1968年にデビューした3代目スカイラインは、旧車の中でも人気が高いモデルです。箱形のスタイリングから「ハコスカ」と呼ばれるようになった3代目スカイラインは、現在でも多くの愛好家に親しまれています。 また、ハコスカの中でも高性能モデルに位置する「2000GT-R」は特に人気が高いです。この3代目スカイラインの高性能モデルに与えられた「GT-R」の名は、現在も日産のスポーツモデルの象徴となっています。 ハコスカのリセールバリューの相場 ハコスカのリセールバリューは、高い状態を維持し続けています。車両の状態にもよりますが、数百万円で買取されることはほぼ確実といえるでしょう。また、高性能モデルであるGT-Rは、1,000万円以上になることも珍しくありません。 ハコスカのリセールバリューが決まる要因 ハコスカのリセールバリューは、車両の状態によって大きく変わります。では、ハコスカのリセールバリューを決める要因は何なのでしょうか。 オリジナル部品が使われている ハコスカは、オリジナル部品が使われているとリセールバリューが高くなりやすいです。エクステリアやインテリアだけでなく、エンジンやトランスミッションなど、内部の部品までオリジナル部品だと買取額が高くなります。また、部品そのものにも高い価値があるため、部品だけでも高価買取されることがあります。 保管状態が良い 車両の保管状態が良いとリセールバリューが高くなります。外装の錆びや塗装の色褪せなどがなく、内装の褪せやひび割れなどがないと高い評価になります。 グレード ハコスカには、4ドア/2ドアをはじめ多種多様のバリエーションが用意されていました。数あるバリエーションの中でも、高性能モデルの「GT-R」は、非常に人気が高くリセールバリューも高い状態となっています。ただし現在は、どのグレードであっても旧車としての価値や希少性が高いため高価買取される可能性が高いです。 ハコスカを高く売る方法 ここからは、ハコスカを高く売る方法を解説します。 ハコスカに対する知見が豊富な業者を選ぶ ハコスカを高く売るためには、ハコスカのことを知り尽くした専門業者に買い取ってもらうことがポイントです。 ハコスカは、先述したように4ドア/2ドアをはじめ、多種多様のバリエーションを用意していました。そのため、ハコスカのどの年式のどのグレードなのかまでわかる専門買取業者でなければ、ハコスカの価値を適正に評価できません。 ハコスカを売却するときは、ハコスカの査定や買取した実績があり、ハコスカの知識が豊富な業者に依頼しましょう。 外装・内装を含め細部までメンテナンスを行う 外装、内装、エンジン、足まわりなど細かな部分までしっかりメンテナンスしておくと高く売れます。 ハコスカは、今や存在そのものに価値があるといっても過言ではないほど希少な車となっています。そのため、車両の状態が良いほど高く売れるのです。 ハコスカをいずれ売却する予定がある方は、定期的にエンジンをかけて走らせたり、外装や内装が劣化しないようこまめにメンテナンスしたりしておきましょう。こまめな手入れで良好な状態を保つことで、売却時に高く評価されます。 ハコスカの魅力と歴史 ハコスカは、1968年7月にフルモデルチェンジしてデビューした3代目スカイライン(C10型)です。 1968年9月には、スカイラインGTのモデルチェンジを発表し、1969年2月に高性能モデル「2000 GT-R」を発売しました。 高性能モデルのGT-Rは、デビュー当初4ドアのみのラインナップでしたが、1970年10月に2ドアハードトップになりました。 GT-Rは、高性能モデルにふさわしい2.0L直列6気筒DOHCエンジン(S20型)を搭載していることが魅力です。最高出力は160馬力でした。2000GTに搭載される2.0L直列6気筒OHC(L20型)の出力が120馬力であったことからも、GT-Rがいかに高性能だったのかがわかるでしょう。 【スカイライン 2000GT-R(2ドアハードトップ)の主要スペック】・全長4,330mm×全幅1,665mm×全高1,370mm・ホイールベース:2,570mm・エンジン:S20型(直列6気筒DOHC/水冷式)・最高出力:160PS/7,000rpm・最大トルク:18.0kgm/5,600rpm・トランスミッション:5速/後1速・最高速度:200km/h※1970年当時のリリース情報より

クラウンマジェスタのリセールは?買取相場や高く売る方法も解説
クラウンマジェスタの売却を検討しており、リセールバリューや買取相場を調べている方もいるでしょう。クラウンマジェスタは、ブランド価値により安定した価格で推移しており、状態次第では相場より高く売却できる可能性があります。 この記事では、クラウンマジェスタの買取相場やリセールバリューのポイントを紹介するとともに、高く売る方法を解説します。 クラウンマジェスタとは クラウンマジェスタとは、1991年〜2018年までトヨタで販売されていたラグジュアリーセダンのことです。クラウンより上位に位置しており、内外装ともにより上級車らしい設計になっています。 1988年に日産の高級車である「シーマ」が大ヒットしたことを受け、トヨタは競合車としてクラウンマジェスタを生産しました。 クラウンマジェスタはクラウンと車名が似ているものの、実際にはプラットホームやボディサイズが異なります。たとえば、外寸はクラウンと比べて下記のようにマジェスタの方が大きくなっています。 ・ホイールベース +50mm・全長 +100mm・全幅 +50mm また、クラウンマジェスタより上位モデルの「セルシオ」と同じく、下記2つのエンジンを採用しており力強い走行が可能です。 ※1UZ-FEは3代目まで、2JZ-GEは2代目まで エンジン 排気量 エンジン出力 型式 V型8気筒 4カム32バルブ 3,968cc 260ps 1UZ-FE 直列6気筒 DOHC24バルブ 2,997cc 230ps 2JZ-GE 以下の採用により乗り心地や安定性、ハンドリング性能も向上しています。 ・4輪ダブルウィッシュボーン式電子制御エアサスペンション・ラック・アンド・ピニオン式ステアリング クラウンマジェスタは、高級感や快適さ、優れた走行性能が魅力のクルマです。 クラウンマジェスタの買取相場 初代と2代目クラウンマジェスタの買取相場を紹介します (2024年8月時点の情報)。 買取相場は週単位で変動するため、売却を検討している場合はこまめに市場の動向をチェックしましょう。 初代(S140型) 初代(S140型)クラウンマジェスタの買取相場は、下記のとおりです。 グレード 買取相場 Aタイプ 5万~20万円 AタイプS 5万~20万円 Bタイプ 5万~20万円 Bタイプ エレクトロマルチビジョン装着車 5万~20万円 Cタイプ 5万~20万円 Cタイプ エレクトロマルチビジョン装着車 5万~20万円 2代目(S150型) 2代目(S150型)クラウンマジェスタの買取相場は、下記のとおりです。 グレード 買取相場 Aタイプ 5万~20万円 Cタイプ 5万~20万円 Cタイプ GPSボイスナビゲーション付EMV装着車 5万~20万円 Eタイプ 5万~20万円 Fタイプ 5万~20万円 クラウンマジェスタのリセールバリューのポイント クラウンマジェスタは高級セダンとしてのブランド価値があるため、買取相場が安定しています。 ただし、クルマの買取価格は下記の要素によって変動します。 ・年式・グレード・走行距離・内外装の状態(塗装やパーツ、シートなど) エンジンや電子デバイスなどの機械系のコンディションも影響するため、必ずしも買取相場 どおりの価格で売却できるとは限りません。 買取相場は、あくまでも目安として参考にしましょう。 クラウンマジェスタを高く売る方法 走行距離をなるべく抑えて、こまめにメンテナンスすることで、クラウンマジェスタの買取価格が高くなる可能性があります。 続いて、クラウンマジェスタを高く売る方法を解説します。 走行距離をなるべく抑える 走行距離をなるべく抑えるほど、クラウンマジェスタの買取価格が高くなる可能性があります。 走行距離は、クルマの査定額に大きな影響を与える重要な要素です。クルマの状態やモデルなどで異なるものの、一般的には走行距離が10万kmを超えたクルマよりも、5万km程度の方が高く売却できます 少しでも高く売りたい場合は、下記のような方法で走行距離を抑えましょう。 ・近距離の移動は徒歩や自転車、公共交通機関を利用する・長距離の移動は電車や飛行機などの交通手段を検討する・通勤や買い物などの日常的な移動ルートを最適化し、無駄な走行を避ける こまめにメンテナンスをする こまめにメンテナンスをして良好な状態を維持すれば、買取価格が高くなる可能性があります。売却を検討している場合は、下記のメンテナンスをこまめに行いましょう。 ・定期点検を必ず実施し、メンテナンスノートに記録を残す・オイルや各種フィルターの交換を推奨時期に行う・洗車やワックスがけを定期的に行い塗装を保護する・内装の掃除をこまめに行い、シートやダッシュボードの劣化を防ぐ エアコンの作動状況や各種ベルトの交換など、細かな部分にも注意を払い、クルマのコンディションを整えましょう。 クラウンマジェスタの売却は旧車王へご相談ください クラウンマジェスタの売却を検討している場合は、ぜひ旧車王へお問い合わせください。旧車王は、旧車に特化して20年以上買取事業を展開しているため、長い歴史をもつクラウンマジェスタを適正に鑑定できます。 クラウンマジェスタは、ブランド価値により買取相場が安定して推移しているものの、買取業者によっては査定額が低くなるケースもあります。少しでも高く売却するためにも、クラウンマジェスタの価値を正しく見極められる旧車王にご相談ください。
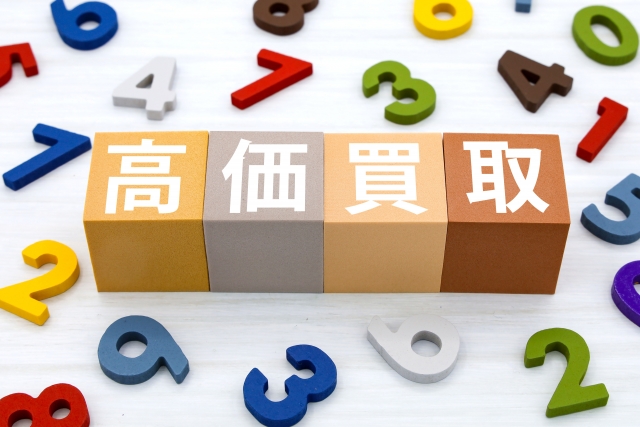
車検切れの車も買取ってもらえる?可能な理由や売る方法を解説
車検が切れてしまったクルマは、そのままでは公道を走行できませんが、中古車買取店に買い取ってもらうことは可能です。 査定額が大幅に下がるケースも基本的にはなく、むしろ費用をかけて車検を通したうえで売却するほうが損をする場合もあります。 この記事は、25年以上にわたって旧車・クラシックカーを15,000台以上買い取りしてきた旧車王が、車検切れのクルマでも買い取ってもらえる理由や売却方法、必要書類などについて詳しく解説します。 車検切れでも買取可能な理由 車検が切れていても、クルマを買い取ってもらうことは可能です。買取業者は、以下のように買い取ったクルマで利益を出すためのさまざまな方法を持っているためです。 ・自社工場や提携工場で車検を通して国内で再販売する ・業者向けのオートオークションで転売する ・日本車の人気が高い海外へ輸出する クルマを買い取った時点で車検が残っていたとしても、販売している間に切れてしまうことも珍しくありません。たとえ切れたとしても、買取業者によっては自社工場や提携工場で費用を抑えて車検を通すことができます。 また、車検は日本の制度であるため、買い取ったクルマを海外に輸出するのであれば、車検切れは問題になりません。 以上の点から、車検切れのみを理由にクルマの買取そのものが拒否されることはほぼないのです。 車検切れが査定額に与える影響 中古車の査定額は、車種、年式、走行距離、内外装の状態などクルマが持つ本来の価値によって決まります。 車検が切れていても、クルマそのものの価値が大幅に減るわけではないため、買取価格が著しく安くなる心配はないといえます。 車検切れの車を売る方法 車検が切れたクルマを売却する方法は「出張査定を利用する」「仮ナンバーを取得して持ち込む」「個人売買で売却する」の主に3つです。それぞれの特徴は以下のとおりです。 出張査定を利用する 出張査定は、自宅や勤務先などの指定する場所に査定士が訪れて、クルマを査定するサービスです。査定料金は基本的に無料であり、査定額に合意した場合はその場で売買契約を結ぶこともできます。 車検が切れているクルマは、そのままでは公道を運転できないため、買取業者の店舗に持ち込んで査定を受けられません。売却の際は、店舗に運び込む必要がなく費用もかからない出張査定を利用するとよいでしょう。 仮ナンバーを取得して持ち込む 仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を取得すると、車検切れのクルマでも公道を走行できるようになるため、買取店に持ち込んで査定してもらえます。 仮ナンバーを取得するためには、市区町村役場の窓口で申請手続きが必要です。申請時に必要なものは以下のとおりです。 ・自動車臨時運行許可申請書 ・自動車損害賠償責任保険証明書の原本 ・自動車を確認できる書類の原本(自動車検査証や登録識別情報等通知書などから1点) ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ・手数料(一般的に750円) 「自賠責保険」の有効期限が切れている場合は、事前に保険会社で再加入の手続きが必要であり、その際に保険料を支払います。 また、仮ナンバーで走行できるのは、申請時に許可されたルートのみであり、有効期間も5日が上限です。申請手続きに手間がかかるうえに制限もあるため、仮ナンバーを取得して買取店に査定してもらうのはあまり現実的な方法ではないといえます。 個人売買で売却する 個人売買は、友人や知人、親族などの個人にクルマを直接売る方法です。買取業者の利益や手数料などの中間マージンが発生しない分、より高値で売却できる可能性があります。 ただし、普通自動車は、車検が切れた状態では名義変更(移転登録)の手続きができません。そのため、売却前に元の所有者の名義で車検を受ける必要があります。 売買契約書の作成や名義変更手続きなどもすべて当事者が行うため、「代金が支払われない」「クルマの名義が一向に変更されない」など、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。 車検切れの車を売る際の注意点 車検切れのクルマを売却する際は、法的な処罰の対象となったり、経済的に損失を負ったりする事態を避けるためにも、以下3つの注意点を押さえましょう。 無車検運転・無保険運行に注意 車検が切れた状態で公道を運転すると「無車検運行」として処罰の対象となります。 また、車検が切れている場合、自賠責保険の保険期間も終了しているケースがほとんどです。自賠責保険が無効な状態で公道を走行することは「無保険運行」という法律違反です。 無車検運行と無保険運行の罰則は以下のとおりです。 違反点数・罰則 無車検運行 違反点数6点 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 無保険運行 違反点数6点 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 両方に違反 違反点数6点 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金 過去3年間の違反点数が累積で6〜8点の場合、30日間の免許停止となり、その期間が終わるまでクルマを運転することはできません。 懲役刑または罰金の対象となる可能性もあるため、少しの距離であっても車検切れのクルマを運転することは避けましょう。 車検を通してから売却するのは損になることがある 車検を受ける場合、車検基本料や法定費用、整備費用などをあわせると10万円前後の費用がかかります。車検を通したとしても、かけた費用を上回る分だけ査定額が増えることはほとんどありません。 査定額の増加分が車検費用を下回って損をする場合も多いため、基本的には車検を通さずに売却したほうがよいといえます。 できるだけ早く売却したほうがよい クルマの資産価値は、時間の経過とともに下落するのが一般的です。特に、年式が古い車種や新しいモデルが登場して型落ちとなった車種は、需要の低下により買取価格が大きく下がる可能性があります。 また、車検切れのクルマを長期間動かさずに放置すると、エンジンやバッテリー、タイヤ、ブレーキなどの劣化が進み、さらに価値が低下する要因となります。 車検切れのクルマを今後も使用する予定がない場合は、価値が大きく下がる前にできるだけ早く売却するとよいでしょう。 車検切れ車の売却に必要な書類 クルマをスムーズに売却するためには、必要書類を事前に準備することが大切です。また、普通自動車と軽自動車では、売却時の必要書類が異なります。以下で詳しく解説します。 普通自動車の必要書類 普通自動車を売却する際の必要書類や準備すべきものは以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証) ・自動車税納税証明書 ・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証) ・リサイクル券 ・印鑑登録証明書 ・実印 ・譲渡証明書(クルマが新しい所有者に譲渡されたことを証明する書類) ・委任状(クルマの売却に関する手続きを委託するための書類) ・住民票(車検証に記載されている住所や姓、所有者などが売り手の実情とは異なる場合に必要な書類) 普通自動車を売却して所有者が変わったときは、運輸局で名義変更の手続きをします。名義変更の際は、譲渡証明書や委任状などの書類が必要となります。 また、譲渡証明書や委任状に実印を押すため、通常は発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が2枚必要です。 軽自動車の必要書類 軽自動車を売却する際の必要書類は以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証) ・軽自動車税納税証明書 ・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証) ・リサイクル券 ・認め印(シャチハタは不可) ・自動車検査証記入申請書 ・住民票(車検証に記載されている住所や姓、所有者などが売り手の実情とは異なる場合に必要) 軽自動車の場合、所有者が変わったときは軽自動車検査協会へ届け出をします。普通自動車に比べて手続きは簡素化されており、認め印で名義変更の手続きができるため、売却時に実印や印鑑証明書は原則として不要です。 ただし、本人確認のために実印と印鑑証明書を求める買取業者もあるため、事前に準備すべきか確認することをおすすめします。 車検切れ車を高く売るためのポイント 車検切れのクルマは、以下のポイントを押さえることでより高く売却することは可能です。 複数業者で査定を比較する 車検切れのクルマを売却するときは、複数の買取業者の査定額を比較するとよいでしょう。 業者ごとに得意な車種や買い取ったクルマの販売網などが異なるため、同じ車種であっても査定額が大きく変わることは珍しくありません。 複数の買取業者にクルマの査定を依頼し、結果を比較することで、より高値で売却できる可能性があります。 状態が悪化する前に売却する 車検が切れていると、長時間動かさないことにより、劣化が進行してクルマの状態が悪化し、査定額が下がる可能性があります。 特に、エンジンや駆動系、ブレーキシステムなどクルマにとって重要な部品にトラブルが生じていると、査定額が大きく下がってしまいかねません。 再び車検を通してクルマを使用する可能性がない場合は、状態が悪化して査定額が下がる前に売却することをおすすめします。 その車種の買取が得意な業者に売却する クルマを売却するときは、その車種の買取が得意な業者を選ぶことが大切です。専門知識や経験などをもとに売却予定のクルマが持つ本来の価値を見抜き、より高い買取額を提示してもらえる可能性があります。 特に、旧車やスポーツモデルなどは、一般的な買取店と専門店で査定額に大きな差が出ることがあります。 車検が切れているクルマが販売開始から10年以上経過している場合は、旧車の買取を専門とする「旧車王」にご相談ください。旧車の知識が豊富なスタッフが愛車を適切に鑑定し、納得の査定額を提案いたします。 まとめ 車検が切れたクルマの買取が拒否されることはなく、買取価格が大きく下がることも基本的にはありません。 ただし、車検切れの状態で公道を走行することは法律違反であり、時間の経過とともにクルマの価値は下がります。将来的に利用する予定がないクルマがある場合は、早急に売却するとよいでしょう。

トヨタ クレスタのリセールバリューは高い!クレスタを高く売る方法や魅力などもあわせて解説
トヨタ クレスタは、姉妹車のマークIIやチェイサーとともに高い人気を誇っていたミドルサイズハードトップ/セダンです。今回は、クレスタのリセールバリューのポイントや高く売るためのコツを紹介します。クレスタを保有していて、売却を検討している方は参考にしてみてください。 クレスタのリセールバリューのポイント トヨタ クレスタのリセールバリューは、旧車人気の影響もあって高い水準で推移しています。世代・年式やグレード、車輌の状態によって買取額に違いがあるものの、販売終了から20年以上が経過した今でも査定額がつくケースがほとんどです。とくに人気が高いのはハイパフォーマンスエンジンを搭載したスポーティなグレードで、車輌の状態がよければ200万円以上の査定額になることもあります。 クレスタを高く売る方法 トヨタ クレスタを高く売るためには、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。ここからは、クレスタをより高く売るためのコツを紹介します。 走行距離をむやみに増やさない クレスタの売却を検討しているのであれば、走行距離をなるべく伸ばさないようにしましょう。クレスタは、最終モデルの販売終了から時間が経過しているため、走行距離が15万kmを超えていることも珍しくありません。そのため、走行距離が短いクレスタは希少価値が高く、高価買取に期待できるでしょう。 メンテナンスを欠かさない クレスタには、ベーシックなグレードからターボエンジンを搭載したスポーティなモデルまで用意されています。グレードに関係なく外装や内装、エンジンをはじめとした走行に関わるパーツのメンテナンスをしておくと、高額査定されやすいでしょう。少しでも高く売りたいと考えているのであれば、定期的に車を動かすとともに、メンテナンスを欠かさないことが大切です。 クレスタの魅力と歴史 トヨタ クレスタは、1980年にデビューしたミドルサイズの4ドアハードトップです。また、クレスタが登場した1980年にオープンした販売チャネル「ビスタ店」の最上位モデルでもあります。 1984年に2代目となり、ハードトップからセダンに変更しました。また、姉妹車であるマークIIやチェイサーより高級感ある内装になっているのも特徴です。 1988年には、3代目へフルモデルチェンジしました。3代目クレスタは、従来の直線基調で角張ったスタイリングから丸みを帯びたデザインとなっています。 1992年に登場した4代目では、ボディが3ナンバーサイズに拡大しました。また、スポーティグレードは「GTツインターボ」から「ツアラー」へ変更され、6気筒エンジンを搭載する「スーパーデラックス」は「スーパールーセント」へ集約されたこともトピックです。 1996年にデビューした5代目は、フォーマルなセダンという位置付けになり、居住性を優先したパッケージングになりました。グレードは、スポーティモデルが「ツアラー」から「ルラーン」へ変更され、最上級グレードは「エクシード」となっています。 どの世代でもエレガントな上級モデルとであることがクレスタの魅力です。 【クレスタ(2代目:GX71)の主要スペック】※2代目クレスタ「2000GTツインターボ」の主要スペック ボディサイズ 全長4,690mm×全幅1,690mm×全高1,385mm エンジン 直列6気筒2.0L(1G-GTEU) 最高出力 185ps/6,200rpm 最大トルク 24.0kgm/3,200rpm 駆動方式 2WD(FR)
